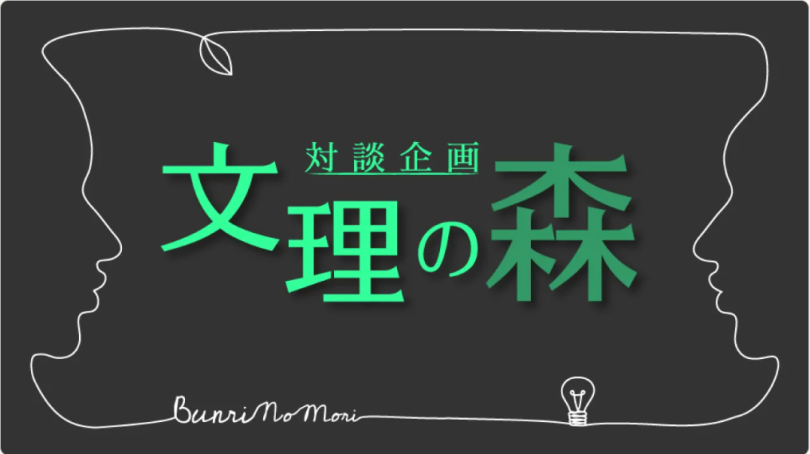サービス本来の価値は、闘い、承認され、新しい自分になること
特にエスノメソドロジー(UCLAの学者が中心となって50年代に生み出した、人と人、人と機械とのインタラクションをビデオで撮って、細かく分析していく研究手法)の観点から、鮨屋をはじめ、数多くのサービス提供者と客の間のインタラクションを分析し、サービス概念を再検討してきた山内裕さんは、現在、京都大学経営管理大学院に在籍し「サービスの文化」に注力して研究を進めています。
「サービスは闘争である」という、これまでのサービス理論を打ち破るテーゼは、私たちが無意識に行っていたサービス本来の価値に気づき、新鮮な視点で物事を見るきっかけを与えてくれています。いったいなぜ、サービスは「闘争」なのか。そして、新しい価値をつくることとはどういうことなのかを伺いました。

ライター
平川 友紀

インタビュアー
西村 勇哉

編集者
増村 江利子
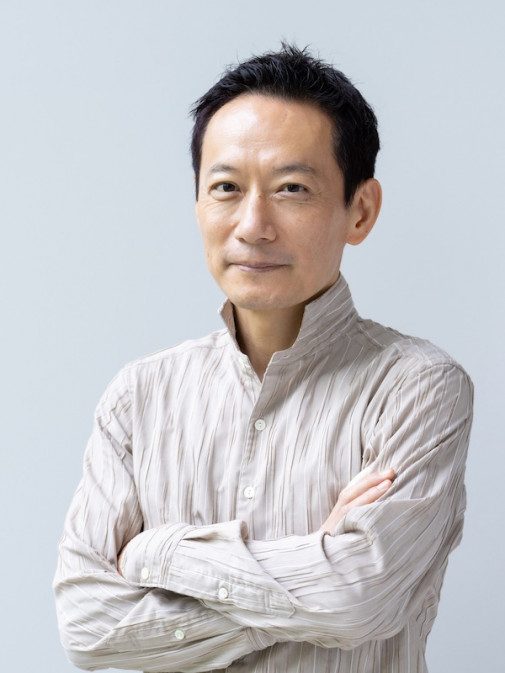
山内裕
京都大学経営管理大学院教授。経済学部・経済学研究科、およびデザインスクールにて兼務。1998年京都大学工学部情報工学科卒業、2000年京都大学情報学修士、2006年UCLA Anderson Schoolにて経営学博士(Ph.D. in Management)。Xerox Palo Alto Research Center研究員を経て、京都大学経営管理大学院に講師として着任。2021年4月より現職。現在は「サービスの文化」に注力して研究している。著書に『「闘争」としてのサービスー顧客インタラクションの研究』、『組織・コミュニティデザイン』(共著)などがある。
ゼロックスに始まり、ゼロックスに戻る
西村勇哉 山内さんは、もともと工学部でコンピューターサイエンスをやっていたのだけれども、そこから経営学にシフトしていったと伺いました。なぜ工学部に入られたのか、最初の関心事はなんだったのかということから聞いていきたいと思います。
山内裕 高校生の時に、ゼロックスの研究所に関する本を読みました。そこには、ゼロックスの研究所がGUI(グラフィカルユーザーインターフェース)やウィンドウシステムを発明したとか、イーサネットを発明したとか、マウスを実用化したとか、とにかくいろいろなことが書いてありました。それを読んでコンピュータサイエンスに興味が湧き、大学も工学部情報工学科に進むことにしたんです。
90年代前半はITがガッと盛り上がりましたが、90年代後半に自分が研究を始めた頃は、コンピュータサイエンスは成熟期に入って、ちょっと落ち着いていた時代でした。その頃のコンピュータサイエンスは、CPUやコンパイラなどの研究ではなく、イメージ的には境界領域が最先端だったんですね。そこで、組織論との境界領域というテーマで、卒論と修論を書きました。
でも実は、大学で実際に勉強してみると、コンピュータサイエンスは人工物を扱うきれいすぎる学問で、自分の肌には合いませんでした。それもあって、博士課程に進む時に、境界領域で学位を取るよりも組織論で学位を取ったほうがいいのではないかと思ったんですね。そして、アメリカのカリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)の経営学の博士課程に入りました。そうしたら、1年目からゼロックスのパロアルト研究所(Palo Alto Research Center、PARC)に出入りすることになり、2004年に最終的に就職したんです。
西村勇哉 すごい。一周回って原点に戻ったんですね。
山内裕 パロアルト研究所は、組織論の一部の研究でも最先端だったんですよね。そういう経緯があって、領域は変わったんですけれども、ゼロックスに戻ってきました。
エスノメソドロジーによるインタラクションの分析

西村勇哉 高校生の時、最初にコンピュータサイエンスに興味をお持ちになった時は「次の時代はコンピュータサイエンスがくるんじゃないか」という、ある種の時代の予兆を感じられていたのではないかと思います。そこから経営学に移ることにした時に、組織論の中でもどのテーマでいくのかということはすでに考えていたのでしょうか。経営学の研究者としての最初のテーマについて教えてください。
山内裕 最初は、組織が新しいことを生み出すプロセスを研究したいと思っていました。いわゆるイノベーションといわれるやつですね。そこから徐々に変わっていきました。重要な点としては、その頃から私は、エスノメソドロジーをやっているんですね。最初にエスノメソドロジーで研究したのは、ゼロックスでコピー機を直す人たち、いわゆるサービステクニシャンです。「コピー機が壊れた」とゼロックスに電話があったら、部品をいっぱいに詰めたバンに乗ってお客さんのところに行って直す。その人たちのあとを、ビデオカメラを回しながらついていって分析したんです。
2000年代前半は、ナレッジシェアリングが非常に盛り上がっていたこともあり、サービステクニシャンの間では、知識共有が積極的に行われていました。それも最初は、すごく簡単に考えていたんですね。もし知らない人がいたら、知っている人に教えてもらえばいいじゃないかと。でも、実際はそういうわけにはいかないんです。なぜなら「知らないものをどうやって聞くのか」ということから始めないといけないからです。もっとややこしいのは、サービステクニシャンは職人みたいなもので、知らないと認めると、自分に能力がないことを認めることになるんです。教える側も、偉そうに教えると角が立ってしまうから気をつけないといけない。だから、非常にややこしいんですね。
例えば、ビデオを見ていると「じゃあこのマシン、もう一回やってみよう」とか、ひとりごとを言ったりするんですね。すると、そのひとりごとを聞いた同僚が食いついて「何をしているんだ?」と言うわけです。「ちょっとこういうエラーコードが出て」と言うと、そこでやっと話が始まる。
つまり、決して聞かないんです。聞いていないということは「助けてくれ」とは言っていないということです。直接聞かずに自分の問題を表現し、他の人が助けてくれるようにしていく。他にも「何々が悪いのであって自分に責任はない」みたいな聞き方とか、いろいろあってですね、やっていくとものすごくおもしろいですよ。そういうことを明らかにして博士論文を書きました。
他にも、銀行での行員とお客さんのやり取りなど、いろいろなインタラクションの分析をしましたが、振り返ってみると、お客さんと接する機会が多いサービスの場面が多かったですね。
西村勇哉 でも、なぜパロアルト研究所を離れて、京大に移られたのでしょうか。パロアルト研究所は、すごく楽しい職場だったのではないかなと思うのですが。
山内裕 2010年ぐらいから、シリコンバレーがだんだん窮屈になってきたんです。私は企業の研究所の研究者でしたが、大企業が研究所をもつということがなくなって、研究者の仕事がだんだん減っていった時代でした。昔はIBMやインテル、HPなど、みんな大きな研究所をもっていたんですけどね。
90年代後半に、スティーブ・ジョブズがAppleに戻って真っ先にしたことは、研究所を解体することでした。Googleには研究所みたいなものはありますけど、昔ながらの研究者がやるような研究というよりも、エンジニアリングに寄った研究をしています。だから、GoogleやFacebookがシリコンバレーの主流になってきた時に、研究者としては生きづらさを感じるようになりました。
私が憧れたシリコンバレーは、ヒッピーの文化が根源にありました。でも、管理が強化されていく方向になっていった時に、自分が憧れたヒッピーの自由な文化が、シリコンバレーから失われていくのを感じたんです。それもあって「いずれは出ていこう」とは思っていました。ちょうどその時、家庭の事情もあって日本に戻ることになり、たまたま京大にくることになりました。私は京大の情報学を出ていますが、経営学や経済学の分野ではまったく縁がありませんでした。本当にたまたま声をかけてもらった感じですね。
よく考えたらサービスばかり研究していた

西村勇哉 研究テーマが「組織論」から「サービス」になるというのは大転換だったと思います。特に「食」にフォーカスを当てられた背景を伺えますか?
山内裕 2010年に京都大学経営管理大学院に着任しました。実は、2010年4月に「サービス価値創造プログラム」というプログラムが立ち上がったんですね。MBAのビジネススクールでサービスという名前をつけたプログラムは、当時、非常に画期的でした。京大はかなり進んでいましたね。
その背景には、2004年頃からサービスが大事だということが、ありとあらゆるところで言われるようになっていたことがありました。その頃、IBMがサービスサイエンスというものを始めています。ITの会社が「これからはサービスだ」と言って、アメリカの大学にサービスのプログラムをつくらせたんです。そういう動きに、日本のIT企業も注目するわけですね。すぐに経済産業省や文部科学省の予算がついて、京大がサービス価値創造プログラムを立ち上げました。そこにポストがあるということで、雇ってもらったんです。
その時は正直、サービスのプログラムと言われても実感がありませんでした。「どうせならおもしろいことを研究したいな」とは思っていましたが、来て2年ぐらいは「何しようかな」と考えながらブラブラしていたんです。
90年代までは、日本企業の研究をすると世界中の人が論文を読んでくれました。でも2010年代には、日本企業は悪い見本みたいに思われるようになっていて、グローバルでは誰も注目しない状態だったんです。だから、日本企業について研究しても興味をもたれないだろうと思いました。
でも周りを見渡せば、ほかにも日本が注目されているものはいっぱいありました。日本食はその典型です。日本の文化的なサービスとして、例えば京都の料亭には、世界中から人がやって来て楽しんでいる。そう思った時に「日本食のサービスの研究をやってみよう」と思ったんですね。
ただ、京都の料亭は部屋で食べることが多いので、データが取りにくいという問題がありました。そこで「鮨屋がいいな」と考えたんですね。鮨屋はカウンターで食べるところがほとんどだからデータが取りやすい。それと、SUSHIが嫌いな人は、世界的にみてもほとんどいないんです。SUSHIは世界中でいいイメージがあるから、たくさんの人に興味をもってもらえるのではないかと思いました。論文を読んでもらえるだろうと。
西村勇哉 確かに個室にカメラが置いてあるのは、違和感があります。鮨屋のほうがデータが取りやすいという観点はおもしろいですね。
山内裕 それと、料亭は決まったコース料理が出てくるのでインタラクションがあまり多くないんですね。その点、鮨屋は一つ一つ注文するのでインタラクションが多い。だから、お好みで食べる店を中心に選びました。
鮨屋の親方は座った瞬間から客を試している
山内裕 東京にある、非常に有名なお店4軒でデータを取らせてもらいましたが、意外だったのは、やりとりがほとんど同じだったことです。どの店も、ほとんど同じタイミングで同じ質問をするんですね。
典型的な例は、最初に入って座った瞬間に「お飲み物どうしましょうか?」とか「お飲み物いかがいたしますか?」と聞くんです。それ自体は普通じゃないですか。だけど、よくよく考えたらメニュー表も渡していないし、説明もしていないし、値段もわからない状態で聞くわけです。だからお客さんは、答えに詰まりながらもなんとか答えるという感じになります。それが、きれいにパターンとして見えてくるんです。
ということは、座った瞬間からお客さんを試しているところがあって、これが鮨屋の緊張感のあらわれであることがわかります。別に、顔がムスッとしているから怖いのではなく、そのやりとりすべてに緊張感があるんですね。
次に「何かお切りしますか?」と聞かれます。私は関西の人間ですから、最初はその意味がわかりませんでした。「お切りしますか?」というのは、お酒を頼んだあと「おつまみを食べますか」と聞いているんです。そこも「はい」と答えるだけではダメです。「はい、白身から」など、何を切るかをちゃんと言わないといけません。そういうことを知らないときちんと楽しめないということが、クリアにわかるんですね。なので、分析はしやすかったですし、すべての店がそうなっているというのが、とてもおもしろかったですね。
西村勇哉 データを取る時は、ご自身が被験者になるんですか?
山内裕 データを取る時は、自分はカメラをセットして引っ込みます。だいたいは、店を貸し切るんですね。ビデオカメラを回す時に何も知らない人が入ってきて、無断で撮影していたら倫理的な問題があるので、貸し切った上で、店に来た人に説明して、入る前に同意書を書いてもらい、普通に店を訪れてもらいます。
西村勇哉 そういう研究に、高級店が協力してくれるものなんですね。
山内裕 それが、意外と断られたことはないんですよ。やってみてわかったのは、鮨屋の親方は店の責任者で、その上には誰もいないわけですよね。そうすると、自分が「いいよ」と言えばいいんです。当然、そのためには何度か通って「実はこういうことを研究しているんです」と説明して、許可をもらうことになります。怖いと評判の親方をわざわざ選んで調査したんですけれども、きちんと説明さえすれば、みなさん意外と優しかったですね。
エスノメソドロジーでの分析には研究者の解釈が入らない
西村勇哉 こうじゃないかと仮定して自分自身が体験し、その結果を記述するというやり方もなくはなかったと思うんですね。でも、あえてビデオを撮ってデータを分析した。ビデオを撮るという方法論の重要性についてもう少し伺えますか。
山内裕 エスノメソドロジーでは、0.2秒の間や、視線をここでこうしたなど、細かいところまですべて分析します。西村さんがおっしゃっているのはエスノグラフィ(訪問観察調査。集団・社会の生活や行動様式を、フィールドワークによって調査する手法や記録文書)だと思いますが、エスノグラフィとエスノメソドロジーの違いは、エスノメソドロジーは研究者が解釈しているわけではないということなんですね。
AさんとBさんのやりとりを分析したとします。視線のあり方や姿勢、間など、そういうものを全部分析すると、Aさんが自分のやっていることをどう見せているのかがわかるんです。そして次に、Bさんがそれをどう理解したのかを分析します。その理解を次の行為でAさんに見せる。それをAさんが理解し、また、どう理解したのかをBさんに見せる。つまりエスノメソドロジーでは、彼らが提示していく理解を分析していくので、研究者の解釈ではないんです。
西村勇哉 なるほど。
山内裕 その水準で全部を分析していくので、Aさんが本当は頭の中で何を考えていたのかということは、そこまで重要ではない。Bさんにとって、Aさんの頭の中は絶対にわからないですし、わからずにやっているという水準こそが重要なんですよね。これがエスノメソドロジーの原理で、細かい分析をするためにはやっぱりビデオが重要なんです。
西村勇哉 そうすると、何が違って見えてくるんでしょうか?
山内裕 例えば注文の時、なぜここで0.5秒のポーズがあったのかを分析すると、そこにはちゃんと納得性があります。でも、やっている時は本人もなぜそうしたのか、完全にはわかっていないんです。でも必ず何かのルールに従いながらやっている。その点は、分析するとすごくよく見えてきます。
西村勇哉 現象としてはあるんだけれども、誰も意識はできていないルールがあるということですね。
山内裕 そうですね。自分自身が客として行くことで、ある程度わかってくることもあるとは思いますが、やはりデータを取ると、それがもっとシステマチックにわかりますね。
サービスは「闘争」である
西村勇哉 そして、鮨屋の研究から「サービスは闘争である」というテーゼが出てきますよね。この言葉の使い方がユニークですよね。なぜ「闘争」という強い言葉を使われたのでしょうか?
山内裕 それについては、実は若干反省もしていて、一番いい言葉だったかどうかはちょっとわからないです。詳しくはあとでご説明します。まず、なぜ闘争と言ったかといいますと、2015年に出した本『「闘争」としてのサービス』をまとめ始めた時に、ある問題にぶつかりました。鮨屋の親方が客を試していることはわかるのですが、なぜ客を試すのかについての説明がつかないんです。なぜなら、それまでのサービスの理論は、基本的にお客さんを喜ばせるということが前提にあるからです。つまり、既存の理論が間違っている、もしくは当てはまらない。そうなると、理論を更新していかないといけないということになりますよね。
そこでふと思いついたのが、ヘーゲルの「主人と奴隷の弁証法」でした。人間は、相手からの承認がほしいんですね。AさんとBさんがいて、お互いに承認がほしいから「自分はこんなにすごいぞ」と自分を証明しようとする。つまり、力の見せあいになって闘いが起こるんです。ヘーゲルはそれを「生死を賭した闘い」と呼んでいます。そして、一方が勝って主人になり、一方が諦めて奴隷になる。主人になった時に初めて、相手から完璧な承認をもらえるわけです。ところが、その時にはすでにその承認には意味がない。奴隷から承認を受けても、主人にとっては何の意味もないからです。
ふと「これと同じだ!」と思ったんですね。鮨屋の親方がお客さんを喜ばせようとしたら「この人は客の評価を気にしている」ということになって、その人からのサービスの価値が毀損されてしまいます。だから、闘争という言葉を使ったのですが、これは理論用語なのです。
西村勇哉 つまり、どちらかが勝ったら終わってしまうので、終わらせずに緊張関係をキープしていくのが大切だということですね。そういう意味では、継続的な関係性になるわけで、店にとっても繰り返しお客さんがやってくることにつながるのかなと思いました。理論だけじゃなく、鮨屋は実際にそうやって今までやってこれた。そしてそういう店が有名になっているわけですよね。
山内裕 そうですね。
西村勇哉 闘わずにもてなす鮨屋ももちろんありますよね。でも高級店は、そういう意味ではだいたい闘っているんですか?
山内裕 高級店はそれなりの価値をつけないといけないので、闘う側面が多くなりますね。お客さん側のおいしいものを食べたいというニーズを満たすだけでは、そこで生まれる価値はたかが知れています。
サービスの大きな価値は、そこで闘い、自分を証明し、新しい自分になって、少しでも承認された感覚を味わえるということ。そこに、お客さんは価値を感じるわけです。だから、高級店には緊張感があるという傾向は顕著だと思いますね。

平川友紀 食べに行っているんだけど、食べるだけじゃない価値をお客さん側も求めている。
山内裕 そういうことですね。だから、お客さんもそこにふさわしい人間を演じたりしますよね。高級なフレンチに行くとテーブルマナーがあって、ワインをリストから選ぶ。注がれたらテイスティングして、気の利いたことを言う、みたいに。そして、だんだんそれに慣れていくと、単においしいワインを飲んだというだけではなく、そこで自分が成長して、新しい自分を獲得したという価値が生まれるんですね。
高級店には、どうしても緊張感がありますよね。なぜかというと、古いブルジョワ的な価値観でつくられているものだからです。テーブルマナーもそうですが、高級店で大切にされているのは、基本的には「形式」なんですよね。それがきちんとできることが大切で、逆に言うと、きちんとできるかどうかを見られて、試されている。
だからブルジョワの人たちは、食べにくい魚をあえて好んだわけです。ちゃんと知っている人でないと、フォークとナイフを使って上手に食べられないから。かつ、味が淡白なので食べた経験がないと評価もできません。食べておいしいだけじゃなく、形式的なテーブルマナーをきちんとやって、見られている緊張感の中で優雅に振る舞える自分、というものがブルジョワの大きな価値だった。だから高級店に行けば行くほど店員が客を見るんです。高級なサービスには、そういう傾向があります。逆にもっと一般的なお店では、店員は客を見ないようにしながら見るんです。
どんなサービスでも
自分がどういう人間かが問われている

西村勇哉 京都で一見さんお断りみたいな店に連れていかれた時に、どう振る舞えばいいのかわからないことがあります。だから「育てる」みたいな関係もあるのかなと思いました。鮨屋とお客さんは1対1の関係ですが、そこに3人目が登場した時にはどうなりますか。
山内裕 年配の人が若い人を経験のために連れて行く、みたいなことはよくあると思いますね。育てるという意味だと、京都では、客が店を育てるという側面も強いです。お客さんが店に対してちゃんと厳しく評価をする。ときには厳しく言うことで、店側に対しても緊張感を保ち続けるということはありますね。鮨屋の場合は特にそうかもしれません。客が経験を積んで味の違いがわかるようになってくると、親方はその上をいかないといけなくなる。そして、親方が何か新しいことを始めると、客もまた経験を積む。その切磋琢磨は常にあります。
でもね、極端なことばかり言っていますけど、鮨屋のサービスだってできない人はできない人で楽しめるようにフォローはしているんですよ。試すけど、すぐにフォローしてヒントを出したりはします。例えば、外国人のお客さんが来たら、応対は全然違うわけですから。
西村勇哉 なるほど。「出て行け」っていうわけじゃないわけですよね。「おまかせで」っていうのであれば、おまかせでも一応楽しめるみたいな。
山内裕 おまかせはダメかもしれません。
西村勇哉 ダメなんだ、ハハハ。
山内裕 お好みで食べる時に「オススメは何?」と聞いたら怒られるというのはあると思います。だけど、フォローはしてくれるんです。昔は「出て行け」って言う親方もいたらしいですけど、今はほとんどいないんじゃないですかね。
西村勇哉 すごくおもしろいんですけど、このおもしろみをどう伝えるのかが意外と難しいなと感じています。例えば、その味をつくるために緊張感が必要、ということだったらわかりやすいのですが、そうじゃないところに価値があると言われると、なかなか伝わりにくいかもなと。
山内裕 そうですね。だから私の反省としては、鮨屋の分析があまりにもインパクトがありすぎたことですね(笑)。「鮨屋の親父はいつも怒っている」みたいなことって、日本人ならなんとなく共有していることじゃないですか。だから「そんな店は嫌だ」という人は多いんです。でも、私が鮨屋の分析を通じて言っていることは、すべてのサービスに共通する、当たり前のことでもあるんですよね。
山内裕 よくスターバックスを例に出すんですけど、スターバックスに行く時って、なんとなく格好に気を使いませんか。そもそも、アメリカ発祥のスターバックスがなぜイタリア語を使っているのでしょうか。要するに、客が知らない単語をわざわざ使っているわけです。それは、客を試しているというのもあるし、「このサービスはあなたにとっての非日常ですよ」というジェスチャーでもあるんですよね。
つまりそういうことは、どんなサービスでもやらないといけないということです。お客さんが慣れ親しんだものを提供しているだけでは価値にならない。「これはあなたが知らないことなんですよ」とやると、お客さん側が背伸びをして知らないものの中で振る舞う。そこで闘争が起きる。
だからスターバックスは、スモール・ミディアム・ラージじゃなく、ショート・トール・グランデと、いきなりイタリア語になるわけです。そうすることによって、価値をつくり出している。鮨屋に限らず、どんなサービスでも同じことなんですよね。店員がニコニコしていて居心地良く見えても、そこではやっぱり自分がどういう人間なのかは問われていると思います。
誰かに見られていなくても、闘争が起こることはある

西村勇哉 そういう意味では、サービスは顧客がある種、一緒にやらないと育っていかないということですよね。でも現代においては、ものすごく簡略化させて、触れ合わなくても完了するようなサービスもあると思うんですね。そうすると、文化としてのサービスはだんだん廃れていくことになるんじゃないかなと思いました。いかにワンクリックで済ませるかという動きに対して、山内さんはどう思われていますか?
山内裕 両方の流れが進んでいますよね。簡単で便利にという動きと、リテラシーがないといけない、ややこしいサービスの重要性に気づく動き。
当然、ECサイトでクリックして買う分には、そのお客さんがどういう人かは問われないわけです。だから、闘争は起こり得ない。一方で、誰かに見られているわけじゃなくても、緊張感が出て闘争が起こることはあるんですね。
例えば、美術館で絵を鑑賞するとします。絵というのは、基本的に画家が誰かに見られることを前提で描いているものです。だから当然、ここには対話があるわけですね。見ている人は、それも織り込み済みで見ている。そして描く人も、見る人の欲望を織り込み済みで描いているわけです。だから、絵を見るとき、自分が見られている感覚があるわけです。
つまり、人が介在しないからといって緊張感がないわけではない。ウイスキーを飲むと、試されている気がしませんか。つくった人に「こうやってつくった」「お前にはわかるか」と問われているというか。コンビニに並んでいるパッケージだって、ちょっと高級感を出そうと思ったら、やっぱりわかりにくくつくるんです。中身がわからないようなデザインにして、余白が多くてわかりにくい言葉を選ぶ。そうすると、そこでもやっぱり闘争が起こります。お前にわかるか、と。だから、ないように見えても闘争はあるんだろうなと。そういう意味では、闘争の含意は非常に広いのだろうとは思っています。
今はカッコつけていないように振る舞うのがカッコいい時代
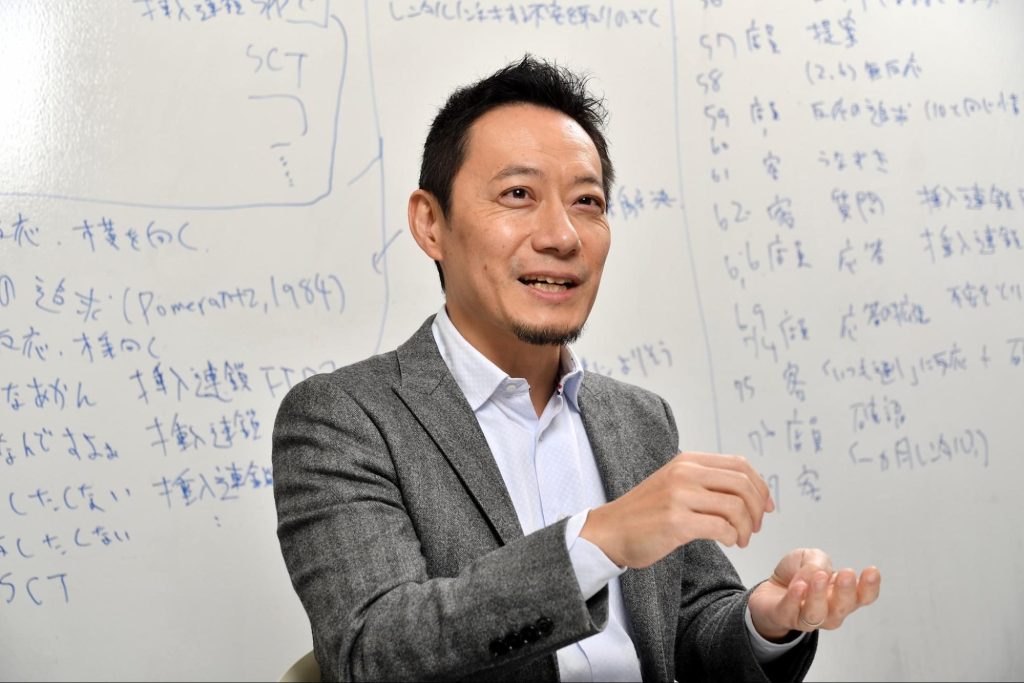
山内裕 ただ、今の若者は明示的な闘争を好まないんですよね。それが先ほど申し上げた「闘争」という言葉を選んだことが失敗だったのではないかという話につながります。つまり、今の若者には、闘争という言葉は、まったくウケないんです。
以前、うちの3回生が1回生にテニス部に入るかオーケストラに入るか迷っていると相談していました。テニス部は楽しいし、勝ったら嬉しいんだけど、負けた相手のことを考えると素直に喜べない。オケはみんなでやるから達成感があってすごく喜べると話していました。要するに、相手を打ち負かすことに対する抵抗感がすごくあるんです。だから、闘争なんていう概念は全然ウケない。けれども、それでも自分が見られていて、自分を証明して承認を得るという側面は、やっぱり重要とされているわけです。
例えば昔、グルメな人は「スノッブ(60年代以前はエリートやブルジョワを指していた。現在は俗物や気取り屋などマイナスのイメージで使われている)」だったんですよね。でも今のグルメは「フーディー(世界中の高級料理を食べ歩く美食家)」と呼ばれています。そして、スノッブだと思われることを極端に嫌がるんです。
フーディーは当然、ミシュランの星付きの店にも行きますし、味の違いにこだわります。でも彼らは、キッチンカーのようなB級グルメも好むし、田舎のおばあちゃんがつくったサルサなんかも好む。メキシコでは、テキーラが上等でメスカルは品質が劣ると言われていますが、フーディーは「メスカルのほうがおいしい」と言うんです。
フーディーがスノッブであることを嫌がるということは、つまり、闘争して自分を見せることを嫌がっているんですね。そして、自分をよく見せようとしないことこそがカッコいいと思っている。ということは、何をやっているかというと、彼らは結局、カッコよくしようとはしているんです。だけど、カッコよくしようとすること自体がカッコ悪いから、カッコよくしようとしていないように振る舞っているんです。
西村勇哉 確かに、あきらかにグルメだよなという人が、カツカレーやラーメンの写真ばかりをSNSに上げたりするんですよね。あれのことだなと思いました。
山内裕 だから、闘争は絶対にしているんです。しているんだけど、しているように見せるのはカッコ悪いんですよ。現代のエリートって、非常に面倒くさいんです。
平川友紀 そういう価値観は時代によって変わっていくんですか?
山内裕 変わりますね。だから、60年代にスノッブがカッコいいとされた価値観はもう通じなくなってきている。今は、カッコよくしていないように振る舞うことがカッコいい時代。これは2000年代の、オバマさんのイデオロギーじゃないかなと思っています。コスモポリタンで、異文化もよくわかっているのがカッコいい、みたいな。伝統的で正統な文化ではなく、ストリートの文化のほうがかっこいいという感じです。
ちなみに2016年には、スノッブでないことをカッコいいとしているエリートに対する異議申し立てが起こっています。それがトランプサポーターです。B級グルメを好むと言いながらマクドナルドをバカにする人たちに、マクドナルドを食べている人たちが異議申し立てをした。エリートの欺瞞をついたわけです。価値観は、時代とともに移り変わっていくんです。
この研究の目的は、新しい視座を提供すること

西村勇哉 一つ気になっているのは、文化について理論化することで、文化が再びつくられることはあるのかという点です。つまり、闘争という概念が伝わることによって、文化が再生産されることはありえるんでしょうか?
山内裕 どうでしょうね。ただ「サービスは闘争である」とわざわざ言った理由の一つは、今もそうでしょうけど、サービスが一方的に喜ばせてもらうもので、金を払っているのだから偉いという理解が世の中に広がっていたからです。そうじゃないだろうという批判的な思いがありました。だから「サービスは闘争である」と言ったことによって、そういう文化が育ってくれたらいいなという期待を込めています。
この研究は、統計的にパターンを出そうとしているわけではなく、新しい視座を提供することが目的の研究です。だから、世の中がこうだと思っていることに「こういう見方もあるよ」「実はこんな価値もあるよ」と提示することが重要だと思っています。
西村勇哉 存在はするんだけれども、みんなが認識できていない盲点を創出していくということですよね。そういった価値の問い直しをしていった先に、こういった分野と協働したい、こういうテーマに取り組みたい、など考えていることは何かありますか?
山内裕 サービスのインプリケーション(含意)は何かというと、価値をどうつくるのかということです。私は2012年からデザインスクールをやっていますが、デザインの世界では、利用者の潜在ニーズを満たすことがデザインだとされているんですね。でも何度も言うように、お客さんを喜ばすだけでは価値は生み出せないんです。
そこで、新しいプロジェクトを立ち上げました。「KYOTO CREATIVE ASSEMBLAGE」という価値創造人材育成プログラムを、文部科学省の「大学等における価値創造人材育成拠点の形成事業」の採択プログラムとして始めたんです。そこでのイノベーションの方法は、今の時代をよく見て、新しい時代の世界観をつくるということです。そして、人々をそこに連れ出していく。連れ出すというのは、新しい世界に足を一歩踏み入れてもらうということです。だから非常に怖くて、ドキドキする体験です。でもそうすることで、初めてそこに価値が生まれるんですね。ニーズを満たして丸く収めるのではなく、むしろ怖い体験をさせる。そのためのアプローチやデザインの方法論に関する新しい創造性教育プログラムとなっていて、これまでの研究も、そこにつながっていくと思っています。
創造性は美学と結びついている

(https://assemblage.kyoto/)。このロゴはプログラムに参画している佐藤可士和氏がデザインした
西村勇哉 今までの価値の考え方は、ニーズを満たすことや役に立つことがベースにあったと思います。でもこのプログラムは、役に立つこととはだいぶ違うところにありますね。なぜ新しい価値を創造していかなければいけないのかと聞かれたら、山内さんだったらどう答えますか?
山内裕 世の中の人はみんな、どうでもいいことをやるのではなく、人々を魅了することをやりたいと思っていると思います。だけどやり方を誤解していて、潜在ニーズを満たしたり、おいしいものを提供したり、おもしろいものを提案したらいいだろうと考えている。新しい価値をつくるということは、その水準の話ではないんですよね。
新しい価値を生み出すには、やはり創造性はとても重要になります。普通、創造性というと内面から湧き出てくるものだと思われていますが、実は違うんです。私は「創造性というのは社会をよく見ることだ」と言っています。逆に言うと、普段、我々はよく見ていないんですよ。だから、よく見た上で、素直に新しい表現をしてあげれば、それはある種の創造性を発揮して人々を魅了し、時代をつくるような新しい価値をつくりあげていくのではないかと思います。
平川友紀 山内さんのブログを拝見していたら「宙吊りにする」という言葉が頻繁に出てきました。これは、360度あらゆる角度から、何者にも縛られない状態で物事を観察するということが、クリエイティブにつながっていくということをおっしゃっているのかなと思いました。今の「創造性とはよく見ること」という話と通じるように思ったのですがいかがですか。
山内裕 簡単に言うと、創造性は美学と結びついているということですね。18世紀末から始まる美学です。美学とは何かというと、結局、宙吊りにするということなんです。美しいものがあるとして、何かの目的に沿って「こうだから美しい」とか「おいしいから美しい」と決めるのではなく「それ自体が美しい」と、目的をいったん外してしまう。アートが役に立たないとよく言いますが、美しいというのは、そもそもそういうものなんですね。だから、宙吊りにするということが創造性につながり、それが価値をつくり出していくということなんです。
-1024x460.png)
https://esse-sense.com/
残念ながら高級鮨店には縁がありませんが(笑)、スターバックスに初めて行った日の緊張感を思い出しました。行列に並び、順番がくるのをドキドキしながら待ち、アタフタしながら「キャラメルマキアート」を注文しました。無事に頼めたときには、なんだか経験値が上がり、成長した気になったものです。
人は、恐怖や不安と葛藤しながらも、新しいもの、未知なるものへの好奇心を抑えられません。そして、好奇心や向上心が不安を上回ったとき、そこに価値を見出していくということに、山内先生のサービス研究を通して気づかされました。そう言われれば確かにそのとおりなのですが、正直、そこまで心の動きをじっと観察したことはありませんでした。これからは店に入ったとき、誰かと対話するときには、楽しみながら、ときには緊張感をもって臨むことができそうです。そこにどう価値を生み出していくのかは自分と相手次第だという、客観的な視点をもつことができたおかげだと思います。
今後も産学連携情報プラットフォーム Philo-では、アカデミアの新たな取り組みや、企業活動を捉え直すきっかけを発信していきたいと思っております。今後もご注目ください。
京大オリジナル株式会社
様々な分野の方の声をお届けしていきます。我々と一緒に、遠い未来像を思索し、世界的な諸課題をどう解決していくかについて議論しませんか?
是非、一度お問い合わせ頂き、貴社と一緒にオリジナリティ溢れるプロジェクト企画ができれば幸いです。
〈こちらよりお問い合わせください〉