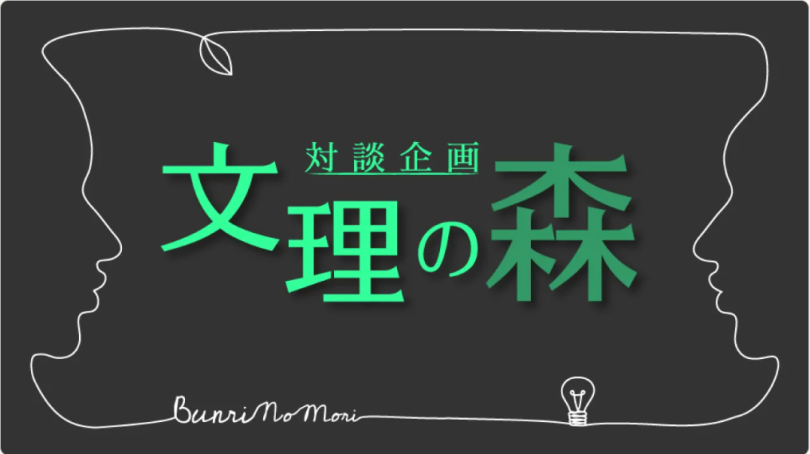「おもろいな」が起点になっている研究は意味がわからなくてもおもしろい
海洋物理学者として地球流体力学の研究を手掛けてきた酒井敏さんは、後年、ヒートアイランド対策に非常に有効な「フラクタル日除け」の開発や、自由な校風で知られる京都大学でもとりわけ個性が際立つ教授らを講師に迎える「京大変人講座」を主催するなど、分野の枠を超えた、多種多様な活動を行なってきました。
「自分がおもしろいかどうか」を基準に、そのときそのときの興味関心を追求してきたという酒井敏さんに、研究者としての思考の片鱗と、その半生を伺いました。

ライター
平川 友紀

インタビュアー
西村 勇哉

編集者
増村 江利子

酒井敏
2023年3月まで京都大学人間・環境学研究科教授。現在は静岡県立大学グローバル地域センター特任教授、副学長。理学博士。専門は地球流体力学。1980年、京都大学理学部卒業。1981年、京都大学大学院理学研究科修士課程中途退学。中退後に助手として採用され、以来、京都大学に40年在籍。大気や海洋の力学的構造の研究のほか、フラクタル構造を応用した日除けを開発するなど、多様な研究を展開している。京都大学の未来に危機感を抱き「京大変人講座」を開講。著書に『京大的アホがなぜ必要か−−カオスな世界の生存戦略』『都市を冷やすフラクタル日除け』『野蛮な大学論』、共著に『京大変人講座』『もっと! 京大変人講座』などがある。
原点は「立ち入り禁止区域で遊ぶ」こと

西村勇哉 酒井さんは京大の理学部に入られたということですが、なぜ理学部を選ばれたのでしょうか。
酒井敏 僕は、もともとは理学より工学への興味が強かったのです。僕の生まれ育った場所は、三保松原で有名な、静岡県の三保半島(みほはんとう)にある工場地帯でした。半島の内側にある折戸湾には、製材前の丸太が筏になって浮かべてあり、湾一面が筏で埋まっていたのです。実家はすぐそばで製材所を営んでいて、子どもの頃は筏の上が遊び場です。でも実はそこは、小学校では「危ないから絶対に行っちゃいけません」と言われているところなんですね。立ち入り禁止区域で遊ぶ。これが原点で、今も僕は、それをこっそりやっているのだと思います。
家が小学校の立ち入り禁止区域の中にあり、近所には友だちが住んでいないから、放課後に一緒に遊ぶ友だちはいませんでした。そのかわり、家にはノコギリやペンチ、金づちなどの道具がいっぱいあったので、自然とものをつくるのが好きになっていきました。大人になったら、ソニーやホンダのように、大きなものづくりの会社に入っておもしろいものをつくるというのが、子どもの頃の夢でした。
しかし1970年前後、ちょうど中学生の頃だったと思います。水俣病や四日市ぜんそく、川崎ぜんそくといった公害が社会問題化したのです。静岡県の場合は製紙工場の排水によるヘドロで田子の浦港が汚染され、非常に大きな社会問題になりました。
僕はそれまで、おもしろいものをつくりたい、楽しいものをつくりたいとなんとなく考えていました。しかし、ただものづくりをしているだけでは、同じことをやってしまうかもしれない。それはなぜかと考えていくと、僕は地球のことを全然知らなかったわけですよね。目の前の機械のことはわかっていても、環境のことや機械の周りのことは何もわかっていない。それだと副作用がたくさん出てくる可能性がある。じゃあものづくりは、周りのことを勉強してからでもいいのではないか、というのが、工学部でなく理学部に進んだ大きな動機です。
もう一つ、理学部に行こうと決めた理由があります。それは、上田誠也さんという東大の先生が書いた『新しい地球観』という本を読んだからです。その本を読んで、僕は初めて大陸移動説を知りました。
正直、地面が動くなんてことはまったく考えていなかったわけです。それが動いて、しかもぶつかると。「ちょっと待って、これ今、下で動いてるわけ!?」というのが、高校生の僕にはものすごく衝撃的でした。
僕は、本を読むのが嫌いです。作文も嫌いで、小学生のときは作文の宿題が出ると本気で熱が出て寝込んでいました。作文は大嫌いだし、読書も大嫌い。1冊読むのに最低1週間はかかっていたと思います。けれども『新しい地球観』は、生まれて初めてひと晩で一気に読みました。
地学は暗記しないといけないことがたくさんある学問です。僕は、覚えるのも苦手だから、地学が嫌いでした。でもその本には「プレートがぶつかって島が寄る、それが山になる。なんとか山脈だのなんとか山地だの、そういう名前はどうでもよろしい」と書いてあった。それにすごく感激して、それなら僕でもわかると思い、おもしろく感じるようになったのです。
公式を自分で導き出さないと気が済まない
西村勇哉 数ある大学の中から京大を選ばれたのは、やはり京大がおもしろそうだと思ったからですか?
酒井敏 地元が静岡県ですから、静岡大学は知っていました。東京大学は、天下の東大だから知っています。でも、ほかの大学は知りませんでした。京大も知らなかった。
高校は進学校に入ったものの、その中では完全に落ちこぼれました。進学校なので進路別クラス編成をしていて、できるクラスとできないクラスに分けられるんです。そうしたら、数学も英語もできないクラスのほうに入りました。英語は仕方がないと思ったのですが、数学もできないクラスに入ったのは自分でもショックでした。でも、本当にわからなかったんですよね。「二次方程式の根の公式を覚えよ」と言われた瞬間に「そんな面倒くさいものを覚えなくてもいいのが数学だろ」と、拒絶反応を起こしたんです。
西村勇哉 ハハハ。なるほど。
酒井敏 はなから覚えるつもりがないから、当然できないですよね。先生に言われても素直に受け取らないので、授業にはまったくついていけませんでした。そのときに、僕は落ちこぼれたから、東大と静大は受からないだろうと思ったわけです。そこでようやくほかの大学を調べ始めて、京大のことを知りました。なんだか自由な学風だっていうから「いいじゃん!」と思って。京大を選んだのはその程度の理由です。
西村勇哉 それで京大に受かっているというのは、結局落ちこぼれていたのかなんなのか。
酒井敏 それはですね、高校に入って、最初は落ちこぼれましたが、2年生になると、突然成績が良くなったのです。ようするに僕は、覚えて答えを出すというやり方がまったくできない。公式を自分で導き出さないと気が済まない質なんですね。だから、導き出せるようになった頃には、できるようになる。わかるまでにすごく時間はかかりますけど、わかるようにはなるのです。
自分にとっておもしろいかどうか

西村勇哉 酒井さんが理学部に行ったのは、ものづくりをする前にまわりの物事の理解を深めるためだったとおっしゃっていました。実際、理学部に行かれて良かったと思いましたか?
酒井敏 理学部でも、やはりカルチャーショックを受けました。僕は工学部か理学部かという二択で迷っていましたが、いずれにしても理系という頭しかありませんでした。しかし、理学部の友人の下宿に行くと、4畳半の下宿にちゃぶ台が置いてあり、その上にはカントやゲーテの本が置いてあるのです。「お前こんなもん読むの?」と聞くと「だっておもしろいから」と言われてね。逆にそいつが僕の部屋に来ると、僕の部屋にはペンチやドライバーが散らばっている。「なんなんだ、これは。どうするんだよ」と聞かれて「どうするって使うだろう」っていうね。それで「ひょっとしてこれは間違ったところに来てしまったのではないか」と思いました。
実は理学部は、文学部とよく似ています。工学部は、経済学部とよく似ているのです。要するに、世の中の役に立つか、立たないか。目の前の問題に対処するのが工学部と経済学部で、そんなことはお構いなしに自分の興味だけで動いていくのが理学部と文学部です。
西村勇哉 なるほど。確かにそうかもしれません。
酒井敏 正直、転学しようかとも思ったぐらいなんですね。
西村勇哉 それは、もっと役に立つことをやりたいということですか?
酒井敏 役に立つことをやりたいというよりも、自分にとっておもしろいことかどうか。もともと自分がおもしろいと思っていたことは、ものをつくるという非常に即物的なことだったわけです。
ただ、わからないなりに理学部で数学を勉強していくうちに、これはこれでおもしろいなとも思えるようになっていきました。中学生のときに、公害問題やプレートテクトニクスを知って「自分が知っている世界ってメチャクチャ狭いじゃん」と思ったときと同じように、さらに世界が広がったという感覚はありました。
全部を知らなくてもいいんだという気づき
酒井敏 ただし、得意だと思っていた数学は、またわからなくなりました。「N次元アフィン空間」というのがありまして、それについて代数の先生が何を言っているのかがさっぱりわかりませんでした。その先生に悪気がないことは、喋っている感じでわかるのです。真剣にこの説明がわかりやすいと信じて説明してくれている。しかも、それは言語としては日本語です。だけど、何度聞いても意味がまったくわかりませんでした。
その講義が理解できるやつがクラスに3人だけいました。「なんでわかるの?」と聞いたら「この教科書は中学のときに読んだ」と言うのです。ところが彼が、2回生になって微分方程式の講義を受けているときに「これどうやって解くの?」と僕に聞いてくるんですね。
彼は、代数はめちゃくちゃ得意で、僕なんかが手の届かないレベルの世界に生きている人間です。ただし代数学は、いろいろなものを文字に置き換えて、その文字の並び方や解法を議論するものだから、抽象的な世界しか彼はわからない。微分方程式は、連続量(水の体積、身長、金額など、計測して得られる量のこと)を求める式です。そういう現実世界に結びつくところになると、彼は途端にわからなくなってしまうわけです。
あるとき、数学の先生に微分方程式の解き方について質問したことがありました。そうしたら「答えが欲しいんですか?」と聞かれました。「存在は証明されているからいいじゃないですか。あることはわかっているのだから、それ以上何がいるんですか」って。
西村勇哉「世界が違う感」がすごいですね。
酒井敏 世界が違うでしょう?数学者にとっては存在するかしないかが重要なので、具体的な答えはどうでもいいんですよ。そこに、まったく興味がないのです。
ところが、解の存在が証明されているということは、僕らがいろいろな問題の答えを考える上ですごく重要です。微分方程式の場合は、唯一解といって、解が一つだけあることが証明されています。一つだけということは、これが答えだと見つけたら、それは正解だということです。だから微分方程式の解き方は、ちゃんと式を満たすことができたら「正解」になるわけです。
それが通用するのは、数学者が微分方程式の解はただ一つだということを証明してくれているからです。つまり「解が存在するから具体的な答えなんかどうでもいいじゃないですか」という人がいないと困るわけですよね。そういうわけのわからない人たちがいないと、僕らは答えを見つけることができない。世間から見ると、数学者のやっていることはまったく役に立たないように見えるのですが、実はものすごく役に立っているわけです。本当に意味がわからないんだけど、彼らがその証明をやってくれているから、僕らも答えが見つけられるというわけです。
西村勇哉 世界は違うけれども、つながっているのですね。
酒井敏 そう。たぶん代数学が得意な彼は、僕らの世界のことはわからない。僕も彼らの世界のことはわからない。だからお互いに、本当のところではコミュニケーションすることができません。だけど、それらがつながって世界はつくられているのだと気がついた瞬間、ああ、別に全部知らなくてもいいんだと思ったわけです。
西村勇哉 向こうでやってくれているから。
酒井敏 そうです。知らないことは任せておこうと。こっちの知っていることをあいつは知らないし、全部知っているやつなんてこの世にはいない。数学がわからないことがものすごく癪だったんですけど、そもそも世界が違うからわからなくて当たり前なのだと思ったら、急に自信をもつことができました。
それでも、なんらかの形でコミュニケーションをとることは絶対に必要です。しかし、その中身については知らなくてもいい。本当に、世界が変わりましたね。それまでは全部知らなきゃダメだと思っていましたから。
西村勇哉 高校生のときの数学の解き方がそうでしたよね。全部がわからないと解けない、みたいな。
酒井敏 そうそう。理学部に進んだのも、公害問題などの周りのことが全部わかってからじゃないと楽しいこともできないと思ったからでした。でも、全部は無理だし、そもそも全部知っているやつなんかどこにもおらんということがやっとわかった。じゃあどうしたらいいかというと、自分がおもしろいと思ったことをやればいいわけですよね。
理学部の研究者だけれども、まず水槽をつくった

西村勇哉 ちなみに酒井さんは、そのあと研究者になるわけですが、最初から研究者になろうと思っていたんですか?
酒井敏 思っていなかったです。なにしろ文章を書くのが大嫌いですから、論文を書くのも嫌なのです。やはり僕は、どちらかといえばものづくりがしたかった。ただ、大学に入ったら海洋研究がおもしろくなってきたんですね。そうしたら、気象は人気がありましたが、海洋の研究室に行く人が誰もいなかった。僕は人気のあるところに割って入るのは嫌なんですけど、誰も行かないところに行くのは好きなんです。
西村勇哉 その性格は、もう話の端々に表れていますね。
酒井敏 だから手を挙げたら、抽選もなく入ることができました。大学院まで進んだら、普通の就職は無理だということはわかっていましたが、専門知識を深めれば、それもなんとかなるんじゃないかとも思いました。先のことはあまり真剣に考えていませんでしたね。
西村勇哉 酒井さんの研究を調べていたら、「中規模渦による深層の南極周極流駆動メカニズム-回転水槽による室内実験-」で「最初に水槽をつくりました」という科研の報告書があったのです。僕は、最初に水槽をつくりましたという理学部の研究者を初めて見ました。1年目にまず水槽をつくるというのは、これはもう工学部じゃないのかと。実はあれを読んだときに、酒井さんは工学が好きなのではなかろうかと思っていたのです。
酒井敏 それは当たっていますね。あれは指導した学生が4回生から修士にかけて取り組んだものですが、当時は、計算機でシミュレーションする走りの時期で、僕もご多分に漏れずやっていたのです。なんでも、最初はカッコいいですよね。でもやってみたら限界もわかりました。当時の計算能力では、渦がゴチャゴチャしているところの細かい計算までは無理だったのです。それと、最初は数値計算の研究で申請すれば科研の審査に通っていましたが、何度かやっているうちに通らなくなってきました。
そうしたらあるとき、審査員をやっていた先生に「酒井さんはなぜ実験で申請しないの?」と言われました。つまり、数値計算をやる人間はいっぱいいるけれども、水槽をつくって実験する研究者は、ひとりもいなかったんですよね。
西村勇哉 僕も報告書を読んだとき、こんなことをする理学系の研究者がいるのかと思いました。
酒井敏 だから「実験で申請を出せば、ほかにいないから通るんじゃない?」と。出してみたら本当に通りました。
ただ、今考えると危ない実験でしたね。学生と一緒にやりましたが、一度バランスを崩して回転水槽が倒れ、暴れ回ったことがありました。あれは、今だったら絶対に通りませんね。昔だからできた研究かもしれません。
西村勇哉 南極の話は、読んでいても楽しかったです。風で海流が東向きになるはずがないだろうと言われている。確かにそうだよなと思うから、水槽をつくって調べることにしました、調べたらやっぱり違いましたと。この報告書、すごくわかりやすいなぁと思いましたし、実験してみないとわからないことがあるのだなと思いました。
ミニカーと車を並べて実験

西村勇哉 もう一つすごくおもしろかったのが、ヒートアイランド現象の研究です。ミニカーと本物の車を並べておいたら、ミニカーは冷たいままだけど、車は熱くなる。小さいものは熱されないということが、ものすごくわかりやすく見えてくる実験だと思いました。
酒井敏 それに気がついたのは、大学が独立行政法人になって、安全衛生管理者を置かなければならなくなったときでした。「お前がいちばん危なそうな実験をしているから、お前が取れ」と言われて、その資格の試験勉強をしていたら、黒球温度計というのが出てきたんですね。普通、気温を測るときは直射日光を当てないように百葉箱をつくってその中に温度計を入れ、空気だけを通して、その空気の温度を測ります。けれども黒球温度計というのは、赤外線も含めて光を全部吸収するのです。
最初にそれを見たときには、そんな温度の測り方をしたら環境の温度としては意味がないだろうと思いました。しかし溶鉱炉のように、赤外線がものすごく強い労働環境であれば、人間はそれを吸収してしまう。黒球温度計は、そういう労働環境における温度を測るための道具としてあったんですね。なるほどと思い、これはヒートアイランド現象の研究にも使えるのではないだろうかと思いました。
由緒正しいベルノン式という黒球温度計があります。16センチの黒い球なのですが、なぜ16センチかというと、人間の頭を想定した大きさになっているからです。しかし、16センチの黒い球をぶら下げて京都市内を歩いていたらどういうことになるかというと、間違いなく警察が飛んできます。
西村勇哉 ハハハ。捕まりますね。
酒井敏 これはもう間違いなく新聞沙汰だと。さすがにちょっと危険だよねということで、もう少し小さいものでなんとかならないかと思い、ピンポン玉を黒く塗ってみたのです。そうしたら、あまり温度が上がりませんでした。
ピンポン玉は約4センチです。黒球温度計の直径が、ちょうど4倍の16センチ。それを調べていくと、伝熱工学の昔の教科書に、気温との温度差は大きさの√(ルート)に比例するということが書いてありました。つまり4倍だと、温度差は2倍になる。ということは、小さいものは熱くならないのではないか。そこで、ミニカーで実験してみたら本当に熱くならなかった。
西村勇哉 しかも、本物の車も並べて測っているのがおもしろいと思いました。
酒井敏 他にも、1メートル50センチと25センチの平たい板を並べるなど、いろいろやってみました。けれども、それだとみんな、1メートル50センチの黒い板が直射日光下ではどれだけ熱くなるのかという想像がつかないんですよね。そうすると「ふーん」で終わってしまう。
でも車が熱くなるというのは、みんながよく知っていることです。だから車とミニカーを並べて「小さいと熱くならないよ」といったほうがすぐ理解できるのです。
西村勇哉 はい。おかげですごく刺さりました。
酒井敏 当時は、実験としてやるなら、ちゃんと空気をコントロールして計測しなさいと、よく言われました。しかし、厳密にコントロールしなければ出現しないような現象は自然界にはありません。いい加減にやってもこうなるというのが重要で、大きさが違うものはなんでもそうなるということこそが大切なんですね。
フラクタル構造の日除けがヒートアイランドを防ぐ

西村勇哉 そこから酒井先生が開発したフラクタル日除けを見ていくと、理解が進みやすかったです。一つの傘ではなく、すごく小さいものが集まって、光だけを通さないようにするということですよね。
酒井敏 小さいものの集合体として光を遮ってやれば、空気自体は通るということですね。これも、いきなりフラクタルに辿り着いたわけではありません。小さいものが熱くならないのはいいのだけれども、タイルみたいに並べてしまえば、結局大きくなって熱くなる。ではどうすればヒートアイランド現象は防げるのかということで悩んでいたんですね。
そのときに、これおもしろいでしょと、数学の先生がおもちゃをつくって見せてくれたことがありました。シェルピンスキー四面体というフラクタル構造の形で、それをある方向から見ると、向こう側が全部隠れて面になる。そこに写真を貼り付けると写真が見えるのですが、四面体を回すとバラバラになってわからなくなるのです。それを見せられて、これはフラクタル次元が2だから、面積があって写真が貼れるのだと言われました。でもそのときは、その重要性が理解できず「数学者って暇ですね」と言ってしまったことを覚えています。
その晩のことです。布団の中で「ちっちゃくすればまちは熱くならない。どうしたらいいのか」と考えていました。要するに、都市の表面がデカいのがいけない。葉っぱぐらいの大きさで、3次元的に分布していればそんなに熱くならないはずなので、2次元のものを小さくちぎって3次元空間に適当にばらまければいいのだけれども、その方法は何かとずっと考えていたら「昼間見たやつがそれじゃん!」と閃いたのです。シェルピンスキー四面体は、2次元なんだけど3次元立体になっている。つまり、2次元なんだけど、3次元にばらまかれているんですね。
通常ならば、2次元のものを細かくちぎって3次元空間にばらまくと、どうしても重なるものが出てきて、穴が空いてしまいます。しかしシェルピンスキー四面体で写真が見える、つまり向こう側が見えなくなるということは、穴が完璧に塞がっているということになります。だからある意味、理想的な形だというわけです。
そこで、画用紙でつくった三角錐でシェルピンスキー四面体をつくり、屋上に置いてサーモグラフィーで計測してみたら、そこだけ温度が全然違ったのです。ちょっと待て、これ、数学者偉いじゃんと。だからね、フラクタルがどういうところにつながるのかは、彼ら数学者はまったく気がついていないわけです。
僕も信じられなかったですね。普通はそういうものを発見したときって喜ぶじゃないですか。でもそのときは喜びよりも、そんなことで今まで悩んでいたのかという「やられた感」ですよね。それと、これをほかの人にいくら口で説明してもわかってもらえないだろう、ものをつくって体験してもらうしかないだろうということも思いました。
西村勇哉 ものをつくって、その下に立ってもらったら涼しいとわかるだろうと。
酒井敏 そうそう。たぶんね、理屈を考えれば考えるほど面倒くさくなるんですよね。

酒井敏 フラクタル図形の中の熱の流れを研究している人は、ほかにいなくもないんです。けれども僕が注目して研究していたのは、その外側の空気の流れです。だからフラクタル図形の外側の空気の流れの性質を説明しなくてはいけないのですが、それをちゃんと系統立てて理屈を付けるのは相当に面倒くさい話です。それをやるとしたら、退職までに間に合わないのではないかと思いました。だからこれは、つくって「どうだ」と言うしかないだろうと。
僕はヒートアイランド学会に入っているのですが、あるとき学会の事務局をやることになったので、そこに間に合わせるようにフラクタル傘をつくりました。そして会長を、最初は朝、まだ日が傾いている時間に連れて行きました。「これで日除けになるの?」とか言われてね。下に入るとスカスカで、青空がよく見えた。そして「お昼になったら呼びますから来てください」と言いました。そして、お昼にそこに座ってもらったら開口一番「何これ?赤外線こないね」って。会長はまさに赤外線に関する研究をされている方だったので、顔の感覚で赤外線が来ていないことがわかったようです。暑く感じるのは、気温が高いからじゃなくて赤外線が来ているかどうか。だから、黒球温度計は意味があった。黒球温度計で測ったものは、肌で感じていることと近いのです。
研究者は、理屈だけで攻めているようで、実際は自分の感覚をすごく大事にしています。自分の感覚に合わないことに理屈をつけられても信じられない。だから多くの研究者の場合、身体感覚が先にあって、後付けで理屈をつけているように思います。その感覚なしで生きていけるのは、基礎物理学者と数学者だけです。
西村勇哉 数学者には、やはり身体感覚はないのですね。
酒井敏 身体感覚のないところで生きていけるのが数学者ですね。それ以外の人は身体感覚のほうが元にある。数学の世界はよくわからなくても、感覚で「やっぱりそうだよね」とわかっているわけです。
西村勇哉 だから結局、わかってもらおうと思ったら、身体感覚がある何かをもっていったほうが伝わる。
酒井敏 それしかないと思うんですね。ヒートアイランド現象が数学と基礎物理の素粒子の問題であれば、そんな必要はない。でも現実問題として、熱いか熱くないかの問題、人間の感覚の問題ですからね。そうなるともう感じてもらうしかない。感じてもらって、みんながそうだよねということをなんとなく常識として思い始めないことには、広がらないだろうと思うんですよね。
研究とは人がやらないことをやることだ

西村勇哉 もともとものづくりの視点があったからこそ、実物をつくろうというふうになっていった。そこで「最初はものをつくりたかった」というところに返ってくるのがおもしろいですね。
酒井敏 僕がものをつくるというのは、やっぱり身体感覚でおもしろいから。それに理屈がくっついてきたらもっとおもしろい。僕が身体感覚でおもしろいと感じることに、僕にはまったく理解ができない数学や物理の理屈がつけられるところが、さらにおもしろいんですよね。
西村勇哉 確かに。同じ世界の中でつながってはいるのですね。その話と「京大変人講座」だったり、著書の『野蛮な大学論』の話はつながってくるのかなと思いました。身体感覚として「これはおもしろいだろう」という感覚がないと研究は始まってこないという話だと思います。
酒井敏 新しいことを言い出すやつというのは、ほかの人から見たらやっぱり変なんですよ。
西村勇哉 それは、褒め言葉としての「変」ですよね。
酒井敏 僕は学生にもよく言っているのです。「研究というのは、人がやらないことをやることだ。人がやらないことをやって褒められるわけはないだろう。怒られるに決まってるだろう」って。
今の学生はね、研究っていうのは勉強の先にあると思っています。でも、いわゆる「勉強ができる」というのは、みんなが知っていることがよくできるという話なんですね。だから客観的に判断できて、順位もつけることができる。しかし、誰もやったことがないことを他の人が判断できるわけはないんですよ。初めてのことをやれば危ないこともあります。「ケガでもしたら迷惑を被るのはこっちだから、余計なことすんな」って怒られるのは当然で。だからこそ、こっそりやらなきゃいけないのだと。
西村勇哉 そうか。こっそりやらなきゃいけないのか。
酒井敏 そうそう。最初はこっそりやって、相当自信をつけてから人に言わなきゃね。「これは絶対こうなる」というぐらい、自分の中で確信をもたないと、人には説明できない。そうやってやらないと、いつまで経っても前に進まないです。だから確信がもてるまでは、こっそりやる。
「寛容」とは、自分がわからないことを放っておくこと
西村勇哉 つまり、こっそりやる場所がなくなると新しいものが生まれてこなくなるということでしょうか。
酒井敏 今は正確性が求められて、こっそりやれないですよね。昔の京大は、あの塀の中だけは違う世界で、文化が違っていました。本来は、言葉で説明しなくても通じるのが文化じゃないですか。
だから、京大の人間同士は「これおもろいね」「おもろいな」と言って通じ合っていたわけです。そして、外にそれを出すといろいろ言われることはわかっているから、外には出してこなかった。つまり、こっそりやっていた。
これは京都だから成立していたのだろうとも思うんです。京都はおもしろいところで、みんな「学生はん」といって学生をとても大事にしてくれる。でも、大事にはするけれども、自分の領域には絶対に入れないのです。親切にはしてくれるんだけど「学生さんお金ないやろ、飯食っていきな」というような親切とは違う。学生は下宿代を払ってくれるお客さん。そこには壁があって、京大で学生運動があっても彼らは近寄らないわけです。「賢い人たちの言うことはようわかりまへんわ」って言ってね。
だから京大が、特別に厳重な壁をつくっていたわけではないのだけれども、その中だけ別世界が存続し得たわけです。京都の人は、京大のことを、どちらかといえば迷惑だと思っている。けれども京都には、応仁の乱からずっと、そういう迷惑なものが身近にあった歴史があるのです。偉い人はケンカばかりしているけれども、庶民には直接関係ない。庶民は庶民で、つかず離れず生き延びてきた歴史があるんですよね。
西村勇哉 その京都の寛容さは、新しいものが生まれるためのカギだと思います。
酒井敏 寛容っていうのは「理解」というふうに言われるのだけれども、理解できるわけがないんですよね。
西村勇哉 実際、変なことやってますからね。
酒井敏 だから寛容っていうのは、自分がわからないことを放っておくということですよね。お互いにわかり合えない、だけど、嬉しそうに喋っているから「こいつは悪いやつじゃない」ということは身体感覚としてわかる。「俺にはわからないけれど、こいつが言っていることはきっと間違いないだろう」と思えるかどうか。
ただ、そういう寛容さをもつためには、本当にヤバいことが起こったときに自分でなんとか対処できる能力がないといけない。最後の手段をもっていないと、相手が何をしでかすかわからなかったら不安でしょうがありません。目の前の危険が顕在化するまでは様子見で、顕在化したらなんとかできるというある種の自信がないと、寛容にはなれないと思うんですね。
わからないことをいかにそのままもっているか

西村勇哉 京大内でも、その寛容さはなくなってきていますか?
酒井敏 そうだと思います。もともと文化として存在し、外に対して説明する必要がなかったから、説明する努力をまったくしてこなかった。言語化されてこなかったので、世間から「ちゃんと説明責任がある」と言われるようになったら反論ができない。じゃあ、なんとかこの文化を言語化しなければいけないだろうというのが、変人講座を始めた理由の一つです。
だから、僕にとっては論文を書くのも変人講座も同じなのです。世の中をどう説得するかという手法が違うだけ。論文も一つのやり方だとは思いますが、僕はそれだけがすべてじゃないと思う。今話していることというのは、今までいろいろなことをやってきた僕の研究の成果です。いろいろやってきて「たぶん、これがええんちゃうか」という、ある意味で、僕としての現時点での結論みたいな話なんですね。
西村勇哉 それは身体感覚の蓄積ですね。
酒井敏 そうそう。で、最終的にこういうことを言うのは、論文という形式よりは、身体感覚が伴う変人講座のほうがいいだろうと思っているのです。変人講座に出てくれた人なんて、僕も正直、全部は理解しきれないですからね。でも、そこがおもしろいんですよ。
この人が見ている世界は俺には見えないけど、でもこの人は仲間だというかね。自分がおもしろいからという理由でやっている人というのは、なんとなくそういうオーラを感じる。おもしろいからやっていて、何かの利益のためにやっているわけではない。何が楽しいのかはわからないけど、そういう人は信用できるわけですね。
西村勇哉 それを今は「何がおもしろいのか説明してください」と真面目に詰められているわけですよね。
酒井敏 そうそう。でも、真面目に詰められちゃうと説明できないですよね。
西村勇哉 わからないから楽しいのに。
酒井敏 つまらないですよね、説明できるものなんて。京大はそういう変なやつのシンボリックみたいなところがありますけど、そこが失われつつあるのは事実です。けれども、こういう変なやつに対する寛容性は、世の中にもいっぱい存在しているわけですよね。
この話は、ラーメン屋の親父がいちばんよくわかってくれるだろうと思っています。「真面目に丹精を込めてつくりました」というだけじゃラーメンは売れない。「マジでこれ入れるの!」「え!と思ったけどうまいじゃん!」っていうのがないとね。
西村勇哉 結局、変なことをやらないと新しいものが生まれずに同じものばかりになっていきますよね。
酒井敏 世の中は基本的にカオスであって、予測できないわけです。だから、想定外のことが起こったときに使えるものというのは、それまでは役に立っていなかったものなんですよ。だから、役に立っていないものをいかにもっているかが大切で、本当はガラクタがいっぱいないといけない。新しいものって、ガラクタの中から生まれてくると思うんですね。
最初から計画を立てて、いろいろなものを組み合わせられるだけの論理的頭脳をもちあわせている人なんてほとんどいない。ある程度形になった、よくわからないガラクタがいくつもあって、組み合わせたらたまたま何かができちゃった。そういうことが起こらないと進歩しないですよね。
西村勇哉 それをあの手この手で説明してみるんですけど、そのあとに結局「それで、どれが役に立つんですか?」と言われてガックリきて、「わからない」と言うと怒られる。けれども「わからないということはわかってるんです」という。
酒井敏 わからないことをいかにそのままもっているかというのは重要で。今はみんな本業があって、なんでも効率的に仕事をして、それ以外のことに手を出さないけれども、副業をやらなかったら、新しいことは絶対に生まれないですよね。僕は副業というものがすごく重要だと思っています。副業をやっていたら、いつの間にかそれが本業のほうに跳ね返ってきて本業が変わっていく。本業が変わるためには、副業をやっていることが大切なんですよね。異世界の存在を知る。それが寛容の意味だと思うんですね。
グレーゾーンは白黒はっきりさせたらいけない
西村勇哉 最後に今、関心のあることを教えてもらってもいいでしょうか。
酒井敏 僕は別に、海洋やヒートアイランド現象の研究に特にこだわりがあるわけではありません。すべての研究は、世の中を楽しくしたいというところから始まっています。
そういう意味では、例えばSDGsというのがあります。17項目あって、矛盾していることも書かれていたりするのですが、そんなこともひっくるめてみんなで幸せになりたいという、ある意味では究極の目標みたいな気はしています。だからこそ、若い人も関心をもっているのではないか。
そうすると「そもそも人間ってなんなんだ」とか「生物ってなんなんだ」というところに行き着きます。僕は生物は苦手だったんですけど、結局のところ、今の世界は「生物ってなんだ?」というところを問わざるを得なくなっていると思っています。だいたい、地球上に最初に誕生した生物にとっては、酸素なんて毒だったわけで、生物に関しては、正解があるわけではないんですよね。
毒(酸素)を出したバカがいて、地球上を毒だらけにした。これを環境破壊と言わずして何を環境破壊というかってね。だけど、さらに今度は、その毒がうまいというバカが出てきて、そいつらが生存競争に勝っちゃったわけです。
だから、最初から正しいことを決めることはできない。そういう世界でどうすればいいかというと、あまり遠くまで見通して計画を立てていたら、カオスの世界では、とてもじゃないけど生きていけないということです。目の前の危険はなんとかしなければならないけれども、あとはなりゆきでやるしかない。なりゆきでやりながら変わっていくのが新生物の進化で、それが人間らしさにつながるのだと思います。ずっとそれでいいかはわからない。でもとりあえず、フェイタル(宿命的、運命的)な問題が起こるまではそれでいいのではないか、というかね。
つまり、グレーゾーンがすごく重要で。正しいか正しくないかというふたつにきれいに分かれるわけではない。本当にヤバいやつと、これはまず間違いないというやつはあるけれども、その間には広大なグレーゾーンがあるわけです。広大なグレーゾーンは、白黒ハッキリさせたらいけないんです。グレーはグレーのまま置いておかないといけない。そこで白黒はっきりさせようとするから、かえって答えがなくなってしまう。もちろん、黒のところはなんとかしなければいけませんよ。
西村勇哉 黒は、なんとかしないと死ぬみたいなやつですね。
酒井敏 そうそうそう。
西村勇哉 グレーは、酒井さんが子どもの頃に遊んでいた筏ですね。
酒井敏 ちょっと怪我してもまあ死にはしない、みたいなね。そういう世界観が、もうちょっと広められたらいいなと思っているんですけど。大学に残っていろいろ考えてきたことも、最終的にはそういうところに行き着くので、この先、流体力学から離れていっても、僕は全然それでいいと思っているんですけどね。
結局答えって、グレーなところからなんとなく出てきちゃうものなんですよね。自分だけの世界で決まるのではなくて、周りからの影響もある。だけど周りのことをすべて理解している人なんて誰もいない。そうすると、自分の預かり知らないところの影響でどんどん変わってくるわけですね。そこでうまくハマるものを、やりながら見つけていくしかない。そういう正解の見つけ方っていうのは、これは生物の本質なのではないかと思うし、それが人間らしさにつながるのかなと思います。
ありそうでなさそうで、やっぱりあるもの
酒井敏 最近、名古屋大学の戸田山和久さんの『哲学入門』という本を読んだら、人間が生きる意味というのは、ありそうでなさそうでやっぱりあるんだと。
西村勇哉 どっちなんだ、ハハハ。
酒井敏 でもそれはすごく的を得ていると僕は思う。ありそうでなさそうでやっぱりあるもの。あるんだけど、そうハッキリしたものじゃないもの。結局それは、いろいろやっているうちになんとなく見つかるものであって、最初からポンとあるわけじゃない。
西村勇哉 なるほど。現象だけあっても、理解しようとしないと近づいていけないですね。
酒井敏 だから、絶対的な正解というものはなくて、のたうちまわっているうちに見つかってくるというか。
西村勇哉 酒井先生も、海洋物理学からヒートアイランドの研究に行き、変人講座まで、いろいろなことをやりながら、今は生物とは何か、みたいなところに辿り着いていますよね。
酒井敏 そうそう。だから、僕も振り返ればいろいろなことをやっています。でも、その瞬間瞬間は、自分が違うことをやっているとは思っていないですからね。自分の中では連続していて、ずっと「なんじゃこれ」って言いながら、目の前に出てきたものを一生懸命やっている。
そのときに何を選ぶかということが、身体感覚のおもしろさというか。「やっているうちにこうなっちゃったんだよ」という感じですね。だから、同じことをもう1回やれと言われたって無理だよね。状況が違いますから。同じことは絶対にできない。
結局、昔「これはなんだ?」と思ったものがどこかで役に立ったり、忘れた頃に返ってくるんですよね。だから捨てられない。かといって、全部もつわけにはいかないから、そこはもう、まさに自分の身体感覚で取捨選択していく。これはもう直感でしかない。黒いところは避けないといけないけれども、グレーのところはギリギリを攻める。どこまで黒に近づけるかはその人の能力によるわけです。
西村勇哉 できるだけギリギリまでいったほうが、きっとおもしろいですね。
酒井敏 ギリギリのところまでいける自信というのが、先ほども言った、ヤバくなったら逃げ帰る自信があるかどうかというところです。人がやっていないところっていうのは、つまり怖いから誰もやっていないわけなので。
でも、攻めてるつもりもない。おもしろいからいっちゃうっていうだけの話で。おもしろいと思ったことにいかに素直になるか。それを僕は、生物としての能力だと思っている。それを今は抑え過ぎていると思うんですよ、理屈でね。
怖いけれどもおもしろい。そのおもしろさに自分の軸足を乗せられるかどうか。そこでいろいろやっているうちに「なんとかなるんじゃないか」という、よくわからない自信が出てきます。だから「死ななきゃいい」っていうのは、僕はすごく重要だと思うんです。
この記事は、株式会社エッセンスの協力を得て製作しています。
https://esse-sense.com/
研究のお話というよりも、研究とは何か、その核心に触れるインタビューでした。酒井さんは、自分が好きなことやおもしろいと思うことを追求し続けた結果、海洋研究に始まり、フラクタル日除けをつくり出したり、京大変人講座を開講したりと、一見脈絡のない多くの取り組みを行なうことになります。そこに通底しているのは「新しいものはグレーゾーンにある役に立たないガラクタから生まれる」という確信です。そのあり方・生き方について、酒井さんのお話は多くの示唆に富んでいました。それは研究に限らず、誰もが新しいものを生み出そうというときに求められる態度なのではないでしょうか。
どう生きるのか迷いが生じたとき、何度でも読み返したいお話の数々です。
今後も産学連携情報プラットフォーム Philo-では、アカデミアの新たな取り組みや、企業活動を捉え直すきっかけを発信していきたいと思っております。今後もご注目ください。
京大オリジナル株式会社
様々な分野の方の声をお届けしていきます。我々と一緒に、遠い未来像を思索し、世界的な諸課題をどう解決していくかについて議論しませんか?
是非、一度お問い合わせ頂き、貴社と一緒にオリジナリティ溢れるプロジェクト企画ができれば幸いです。
〈こちらよりお問い合わせください〉
-1024x460.png)