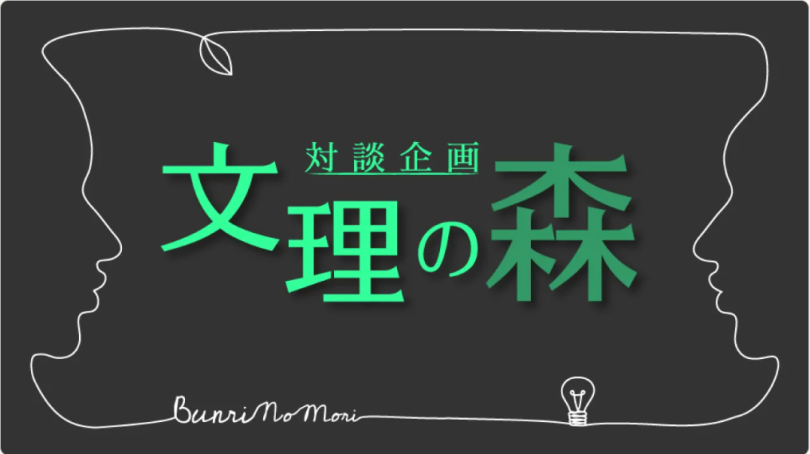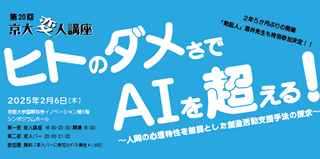【インタビュー】京大発アントレプレナーに聞く。学生と研究者、それぞれの起業のリアル
京大オリジナル株式会社では、京大発スタートアップの育成や支援につながる新規事業の展開を模索しており、いくつかのプロジェクトが進行中です。
今回は、京都大学に在籍しながらスタートアップを立ち上げた理学研究科修士2年の山本 智一さんと、京都大学の特定研究員として勤務しながら、スタートアップ立ち上げに向けた活動をしている奥田 結衣 先生をお招きし、京大発アントレプレナーのリアルについて伺いました。(インタビュアー:京大オリジナル 久保園 遥)
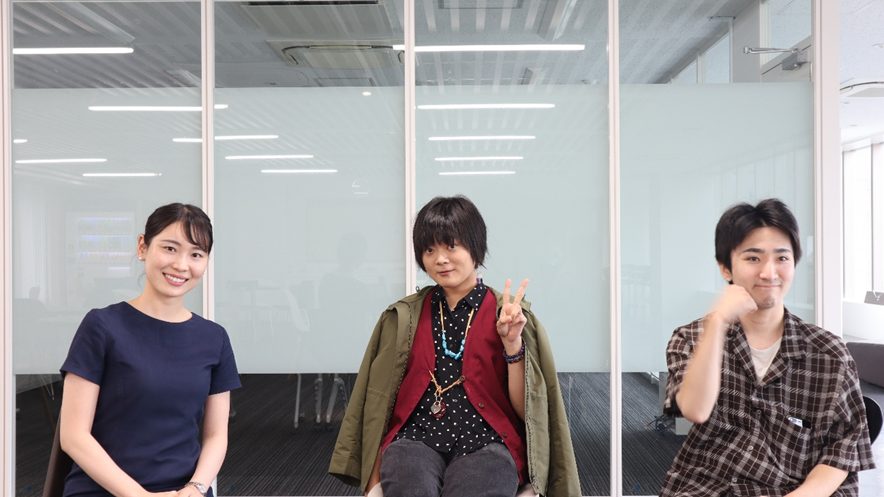
「憧れ」や「ただの選択肢」から始まったスタートアップへの道
久保園 まずは、お二人の簡単な自己紹介と、それぞれのスタートアップの概要についてお聞かせください。
山本 京大の理学研究科修士2年で、バイオインフォマティクスの研究室にいます。ただ、今は休学して、株式会社whickerの代表取締役をやっています。
株式会社whickerは、若者とシニアの方をマッチングする「まごとも」というサービスを運営している会社です。具体的なサービス内容としては、若者がシニアの方の自宅へ訪問して、一緒に外出したり、スマホやタブレットの使い方を教えたりするなど、介護保険ではカバーできないご要望にお応えしつつ、シニアの方に若い世代との交流を提供することで精神的な活力を得ていただくというものになります。
ユーザーはシニアの方ですが、依頼主はそのご家族です。
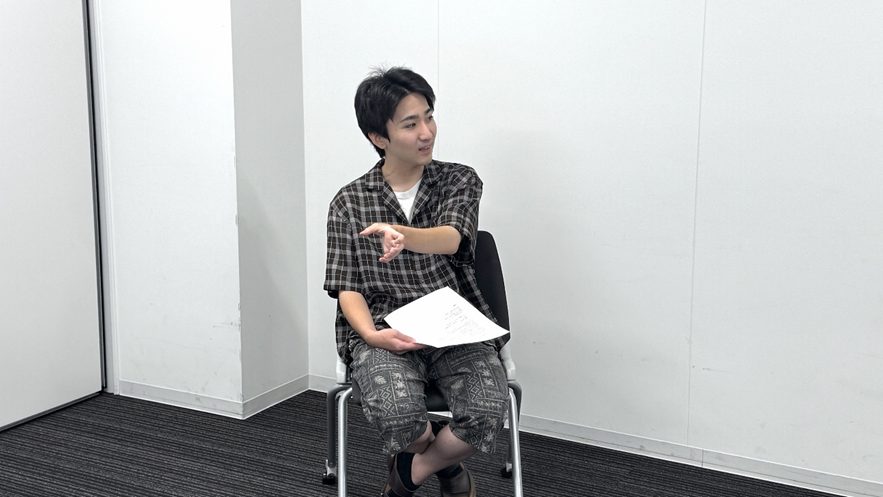
久保園 ありがとうございます。続いて、奥田先生も自己紹介をお願いします。
奥田 京大の農学研究科で特定研究員をしています。化学メーカーと一緒に、“今までにない自然由来の材料を作る”という研究に取り組んでいます。また科学研究費助成事業(科研費)の若手研究にも採択されており、地球に豊富に存在する植物資源と無機物(たとえば骨や砂など)を複合化することで、丈夫なバイオマス材料を作る研究をしています。
そういった材料をシーズとして、京大発スタートアップを立ち上げられればということで、主に外部の支援機関と交流しながら、準備を進めている感じですね。
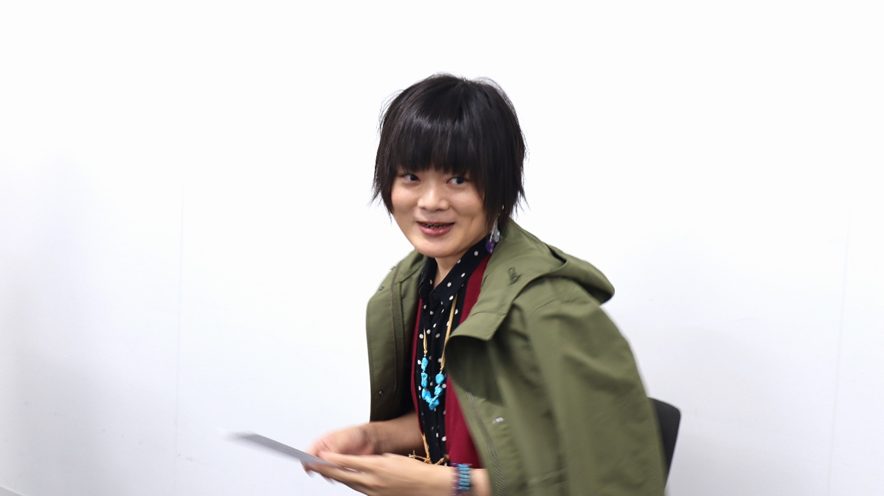
久保園 ありがとうございます。山本さんはすでに起業されていて、奥田先生は起業に向けて活動中ということですが、そもそもどうして起業しようと思ったのでしょうか。
奥田 正直に言うと、最初は憧れでした。鳥取大学で教鞭をとられていた伊福伸介教授(現所属: 京都大学 生存圏研究所)は、カニの甲羅からとった繊維で、製品を作る研究をされています。伊福教授は、当時在籍されていた鳥取大学で、鳥取大学発スタートアップ「マリンナノファイバー」を立ち上げられました。
自分は「マリンナノファイバー」を修士1年生の頃に知り、「かっこいい!!」と思って。だから最初は本当にただの憧れです。
その後、大学発スタートアップにはどういうメリットがあるか考えました。
自分は大学が好きですが、特にこれからの時代は勉強だけで人はついてこないと思っています。だからこそ大学は、ちゃんとお金になること、ビジネスになることをやって、「社会の血の巡りを良くしているぞ」ってアピールしていかないとダメだと。自分が起業することで、「大学は勉強だけでなく、実際にビジネスも生み出して社会に貢献していける意義のある場所だ」ということを証明できればとの思いで活動しています。
久保園 きっかけは憧れだったかもしれませんが、現在は社会にどういうインパクトを残すかに動機も変化しているのですね。続いて、山本さんも起業の動機についてご教示いただけますか。
山本 僕は学生で社会人経験もなかったので、起業するのも社会人になるのも、どちらも同じ感覚というか、単純に進路として起業を選んだだけですね。
僕は視野の広がる体験をすることが大事だと思っていて、取りあえず何でもやってみようという性格もあり、学生時代からアクティブに活動していました。いろいろチャレンジしている過程で、選択肢の一つに起業が出てきて、最終的に起業を選んだのが正直なところです。
久保園 ありがとうございます。山本さんは、なんと調理師免許もお持ちだと伺いました。ところで、起業しようとして「まごとも」が生まれたのか、「まごとも」を作りたくて起業したのか、どちらでしょうか?
山本 前者ですね。先に起業しようと思って、「何しよっかな〜」と事業を考えていきました。
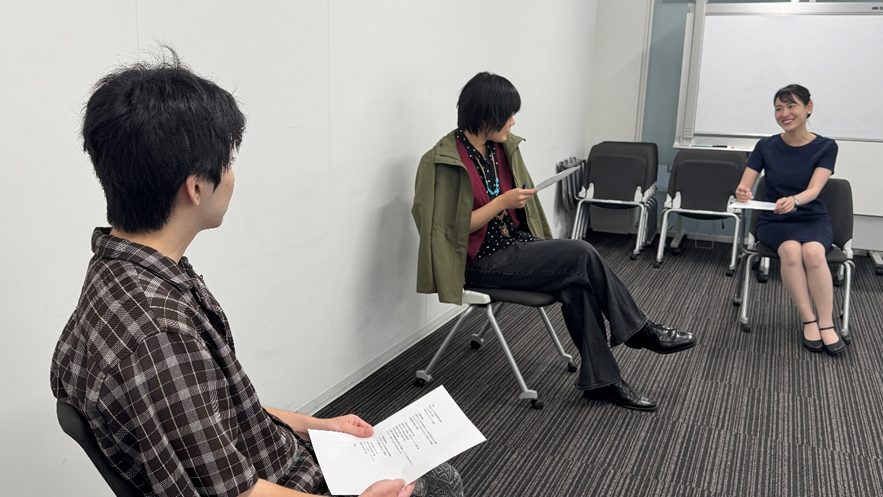
大学発スタートアップの立ち上げは、やっぱり大変
久保園 「まごとも」の起業には、様々な困難があったと思うのですが、特に大変だったことは何ですか?
山本 正直、課題だらけだったのでどれが一番というのはないですね。契約書を作るのも難しかったし、アプリを作りたくてもエンジニアの知り合いがいない。そういう壁は多々ありましたけど、「全部乗り越えていきゃいいじゃん、何とかなるさ」みたいな感覚で生きてきているので。
久保園 そうなのですね。奥田先生は、外部の支援機関だけではなく、京大の成長戦略本部にもご相談されたと伺いました。何か具体的な課題があったからでしょうか?
奥田 これまでも様々な研究費、また助成金に申請してきたのですが、これからさらに様々なファンドに申請して、自分で自由に使える大きなお金を獲得するためです。もちろん、大学の研究にも力を入れる必要はありますが、だからといって、そういう準備をせずに、研究だけやっておきますというのも違うと思うので。
久保園 精力的に活動されていますね。
奥田 まあ、課題はいろいろありますよ。しかも、研究者がやる大学発スタートアップって結構ややこしくて。例えば、稼いだお金はどこに行くのかとか。
久保園 そうですよね。知財まわりとか。
奥田 そうです。しかも、自分はもともと同志社大学の出身ですよね。今は京大にいますが、京大発スタートアップを立ち上げるとなったときに、その辺りがややこしくなりそうで。だから今は視野を広げて考えるようにしています。
久保園 研究者が起業する際の困難について、詳しく共有いただき、ありがとうございます。
奥田 今考えているのは、計画書を書いて、いろんなところに申請しまくって、まずは多額な資金を得たいということです。
久保園 応援しています。ちなみに、奥田先生の起業は、ご自身が経営者になる想定でしょうか。
奥田 そうです。自分がリーダーです(笑)。
学生として、研究者として、京大発スタートアップをめざす上での注意点
久保園 続いて質問です。今後、京大発アントレプレナーがぶつかるだろう課題や、気をつけたほうがいい点はありますか?
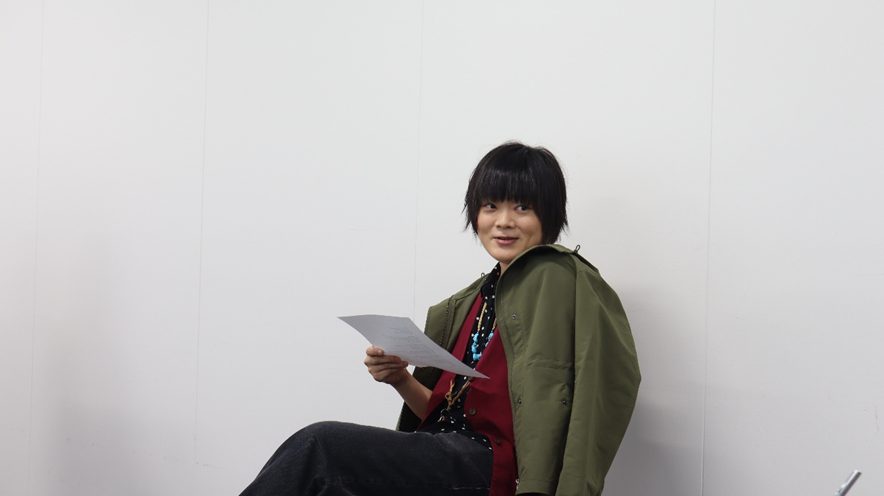
山本 学生起業家でやっていくには、大人の力を借りる場面も多々出てくるので、騙されないようにすることですかね。自分たちは運よく騙されたりはしませんでしたが、ビジネス経験のある起業家でも、言いくるめられてしまった話はよく聞くので。学生起業家による京大発スタートアップであれば、なおさら大人の力を借りないといけないシーンも多いから、そこは重要かなと思います。
久保園 ありがとうございます。奥田先生は、起業に向かって活動中ですが、研究との両立は難しいですか?
奥田 そこが問題で。研究の成果をビジネスにするなら、研究をするほど起業につながるのではないかって思いがちですが・・・。大学での研究となると、誰の権利になるのかが、ややこしい。
久保園 そういった知財関係は、どなたかに相談することはありますか?
奥田 知財関係は外部の支援機関に相談していますね。外部の支援機関からは、自分のビジネス化に向けた準備の前に、助教のポジションを得たほうがいいという意見をもらっています。
理想としては、化学メーカーとの共同研究員を経て、助教などの次のポジションを得る。その後起業して、京大や化学メーカーとのWin-Winを目指すのが一番美しい形だと思っています。いろんなつながりを大切にしながら、みんなにとってよい道を探っていければと思っています。
久保園 今、奥田先生の周りに、同じように研究をしながら将来的に起業を考えている方はいますか?
奥田 京大の中では会ったことがないですね。ただ、自分が参加している外部の支援機関のピッチイベントには、他大学で助教をやりながら大学発スタートアップを立ち上げている先生がいます。研究員、ポスドクの状態で、大学発スタートアップという方には、私はまだお会いしたことがりません。
久保園 ポスドクで起業を志すのは、珍しいことなのですね。
奥田 自分が知らないだけかもしれませんけどね。多分、ポスドクからでも起業できないわけではないと思います。ただ、話を聞くかぎりでは、助教とか先生のポジションになってからのほうがやりやすいだろうなと感じました。
久保園 ありがとうございます。学生・研究者それぞれの起業のリアルについて伺いました。次の記事では、京大発アントレプレナーが求める支援について、深堀していきます。
二人の求める支援を紹介した記事はこちら
https://philo.saci.kyoto-u.ac.jp/2024/12/kuo25/

産学連携情報プラットフォーム Philo-では、アカデミアの新たな取り組みや、企業活動を捉え直すきっかけを発信していきたいと思っております。今後もご注目ください。
京大オリジナル株式会社
京都大学では産学連携の取り組みのひとつとして、京大発スタートアップ創出支援に力を入れており、さまざまな支援策の拡充を進めています。
興味を持たれた企業の皆様は是非、一度お問い合わせ頂き、貴社と一緒にオリジナリティ溢れるプロジェクト企画ができれば幸いです。〈こちらよりお問い合わせください〉