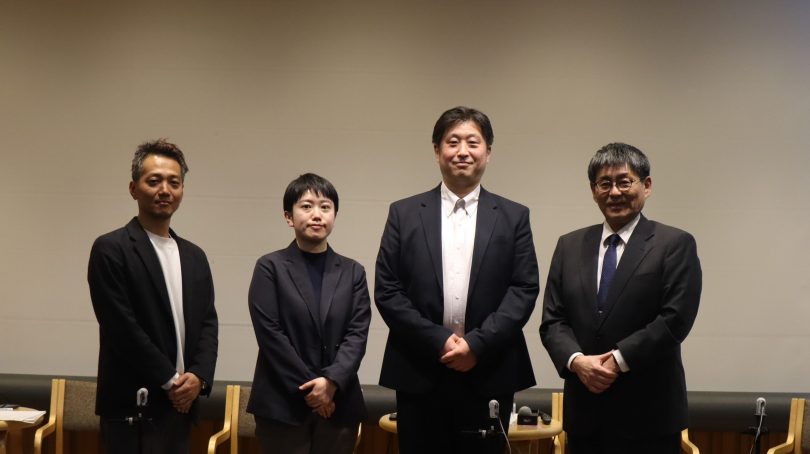「70億の力」≒「究極の選択」≒マシな未来
大庭弘継さんは、海上自衛隊に8年間勤務したあとに研究者になったという異色の経歴の持ち主です。子どもの頃から国際政治に興味をもち、自衛隊に入隊。その後もさまざまな国際政治の問題に向き合ってきました。
さらに近年は、あらゆる分野に内在する、誰もが納得する正解が存在しない問題「究極の選択」をテーマに、分野を横断した研究を続けています。正解が存在しないからこそ、自分たちの運命を自分たちで決める必要がある。そのために「究極の選択」と向き合う社会をつくりたいという大庭さんに、その真意と、現場を大切にしてきたからこそ見えてきた未来について伺いました。

ライター
平川 友紀

インタビュアー
西村 勇哉

編集者
増村 江利子

大庭 弘継
京都大学大学院文学研究科研究員。 1975年生まれ。京都大学中退後、海上自衛隊に8年間勤務。九州大学で国際政治を専攻し単位修得退学、博士(比較社会文化)。南山大学社会倫理研究所専任講師などを経て、2016年より現職。専門は国際政治学、応用哲学・倫理学。研究テーマは、戦争・人道危機、生命(科学)倫理、技術哲学・トランス・サイエンス問題など多岐に渡る。著書に『国際政治のモラル・アポリア』(共編著、ナカニシヤ出版)など。
国際政治に興味をもつきっかけは、冷戦の終結

西村 大庭さんは、自衛隊に8年間いて、それから研究者になられたんですよね。とても変わった経歴なので、まずは少年時代から自衛隊を経て、今に至るまでの経緯を伺えたらと思います。
大庭弘継 僕が中学生の頃、冷戦が終わりました。ベルリンの壁が崩壊し、ルーマニアのチャウシェスク大統領が公開処刑されるなど、国際政治の激動を身近に感じていたんです。中学生がそういうことに興味をもつのかと思われるかもしれないですけど、なぜか僕はずっと見ていたんです。テレビにかじりついて、毎日のように世界が変わっていくことに驚きを覚えていました。
きっかけはよく覚えています。中学2年の夏休みの登校日、帰宅直後に読んだ日経新聞夕刊です。日経新聞は普段、経済記事が一面です。ところがその日は「ハンガリー国境から東ドイツ市民が大脱出」と報じていました。
「日経の一面に政治記事、珍しいぞ」と思って読んだんです。でも記事には、ただ「脱出」としか書いてない。何がすごいのか、中学2年の僕にはよくわからなかった。ですが、それから、あっというまに世界が変わっていったんです。
脱出する人が、1千人から5千人、5千人から1万人とどんどん増え、脈略もわからず、いろんな国が共産主義を放棄した。そのピークは、みなさんご存知のベルリンの壁の崩壊です。そのとき「世界はいきなり変わる」ということを実感し、国際政治に関心を抱きました。

大庭弘継 じゃあ、そのあとになぜ自衛隊に入ったのか。自衛隊って、要は軍事力です。軍事力は、善きにしろ悪しきにしろ、世界を大きく動かします。89年の冷戦終結もそうだった。ところが日本では、軍事は嫌悪されている。それはおかしい。本当に世界を語ろうとするなら軍事を知るべきではないか、そう考えました。もうひとつは、単純に「自衛隊に入れば海外に行けるし、国際的に活躍できる」と思ったからです。今は留学も普通かもしれません。でも90年代はまだ、海外のハードルは高かった。そんなとき、湾岸戦争があり、自衛隊の派遣があり。軍事への関心もあって、自衛隊に入ろうと思ったんです。
西村勇哉 でも、そこから8年間いたというのは長いですよね。
大庭弘継 そうですか。自衛隊は30歳までと考えていました。そして、辞める頃に関心があったのが、偉い人の言うことと現場で起こることの乖離でした。
偉い人々は国防を崇高に語るけど、その人たちは現場を経験していない。自分が現場にいたからこそ「経験がないのによく言えるな」という鬱憤が溜まっていました。ただ、間違っていると思っても、どうすればいいのかはよくわからなかった。それで、人生のリセットとして大学院に進み、国際政治を学ぶことにしました。ただそのときは、研究者になるつもりはまったくありませんでした。
博士3年のとき、南山大学の「社会倫理研究奨励賞」をたまたま受賞しました。授賞式のとき、「仕事がないんですけど、どこか紹介してくれませんか?」と冗談で言ったんです。そうしたら「じゃあうちに来たら」という話になり、南山大学で働けることになった。最初は無給の研究員、1年後に、期限つきの正式雇用になりました。その後、ご縁があって京大の研究員となり、今に至ります。
平川 つまり、いつのまにか、流れで研究者になってしまったんですね(笑)。
国際政治の研究者がパンデミックのシンポジウムを開催

西村勇哉 大庭さんにぜひお聞きしたかったのが、2014年のパンデミックの公開シンポジウムの話と「スレブレニツァの虐殺」の論文の話です。まず、国際政治を学んでいた大庭さんが、なぜパンデミックのシンポジウムを開催するに至ったのでしょうか。
大庭弘継 国際政治でアフリカの人道問題を調べていくと、感染症の問題が必ず出てくる。そこからパンデミックについて考え始めました。もしも感染症が爆発的に流行したら、多くの犠牲者が出るだろう、と。2009年には、豚由来のH1N1の新型インフルエンザで、パンデミックが宣言されましたよね。これが、より強毒型だったらとんでもないことになっていたと、大きな問題意識をもっていました。
そんなとき、シンポジウムでも登壇いただいた林芳紀さんから、同じくシンポジウムに登壇いただいた手塚洋輔さんの著書『戦後行政の構造とディレンマ―予防接種行政の変遷』を紹介されました。そこには、感染症への対処の問題は、ワクチンについて「接種する」「接種しない」の判断が、振り子のように揺れることだと指摘されていました。
最初は「公衆衛生のために、ワクチンを強制接種しましょう」となりますが、副作用で大勢の人が亡くなると、やっぱり強制はダメだと不強制になるんです。でも、また感染症が蔓延すると、やっぱり強制だ、となる。つまり、判断が振り子のように揺れ動くんです。
じつはそれは、私が研究している「人道的介入」での、重要なテーゼなんです。人道的介入は、劇薬です。軍事介入して成功したら虐殺は生じない。ところが、軍事介入による犠牲者は出る。つまり人道的介入というのは、100万人を救うために10万人を巻き添えにしてよいか、という倫理問題を抱えています。ですが、この倫理問題の判断は、振り子のように揺れ動く。
たとえばルワンダ虐殺では80万人が殺されました。なんで介入しなかったんだということで、国際世論は軍事介入にスタンバイします。そして、旧ユーゴスラビアのコソボでは、軍事介入しました。しかしコソボの軍事介入に対し、なんて酷いことをするんだと、国際世論から非難を浴びた。そして、軍事介入に対して消極的になる。でも消極的なときに再び虐殺が起きると、そのとき、国際社会は見ているだけになり、今度は見殺しにしたと非難され、次回は軍事介入する、と揺れ動くんです。
この介入と不介入を振り子のように繰り返す人道的介入。そのうえでの「人道的介入の是非」が、私の大きな研究テーマでした。
感染症のパンデミックでも同じことが起こっている。だとすると、見かけは違うが同じ問題を抱えているのではないか。人道的介入もパンデミックも、危機が起こってからでは対処できない。危機が起こる前にどう対処すべきか、あらかじめ俎上(そじょう)に乗せておかないと後手に回るのではないか、と思いました。
同じ問題を抱えていても、軍事は毛嫌いされる。だがパンデミックは、万人に共通の危機だ。それなら、パンデミックは共感を得たうえで、同じ問題を解決する糸口になるのではないか。そう考え、シンポジウムを企画したんです。

西村勇哉 まさに「事前に準備することの価値」だと思うんですけど、それってすごく難しいなとも思うんです。日々、目の前にあるものをとりあえずやっつけたい気持ちが優先されて、振り返って準備することはどうしても後回しにされてしまう。そこを抜けるための思考プロセスってあるんでしょうか?
大庭弘継 自分のブレはなかなか自覚できないので、記録することが必要です。たとえば毎回投票に行っても、自分の過去の投票先と判断を覚えていない。僕は、過去の自分の判断は記録しています。秘密投票制は選挙の原則ですし、他人に教える必要はないですが、自分に対しては情報を残す必要があります。
西村勇哉 今、毎回誰に投票していたかなと考えたんですけど、確かにちょっとブレているかもしれないと思いました。投票前はきちんと情報を集めてから誰に投票するかを決めていますが、これまでの自分がどうで、その結果がどうだったのかという検証はしていなかったですね。そういう記録をつけておくというのは面白い気がします。

「究極の選択」とは、誰もが納得する正解が存在しない選択

「究極の選択」ライトユニットのホームページより。ズシリとくるコピーが並ぶ。ホームページでは選択と意見を求めるアンケートも実施している。ぜひご参加を
大庭弘継 さらに僕は、そこから「究極の選択」というプロジェクトを進めています。これはまさに、僕がやっていた「人道的介入の是非」の研究から出発して、パンデミックのように、ほかの分野でも同じような問題があることがきっかけで始まったものです。
「人道的介入の是非」という研究テーマでは、同じ問題をもつ他分野の方から、嫌悪感を抱かれる。だったら、すぐに連想でき一緒に使えるツールをつくろうと考えました。そこで、誰もが難しさを共感でき、また、正解がないことを直感できるテーマとして「究極の選択」という言葉を借用したんです。
パンデミックでワクチンをどうするのか、人道的介入をするか否か、どちらも自分たちの運命を決める重要な究極の選択です。それを政治家にお任せするのではなく、自分たちがオフィシャルな形で意思表明できる場が必要です。そうじゃないと、自分の生死を他人に勝手に決められてしまうことになると思いました。
僕が南山大学にいた頃にお世話になったシーゲル神父という先生がいました。シーゲル神父がよく補完性の原理「Principle of Subsidiarity」を言っていたんです。
これは菅前首相のキャッチフレーズ「自助、共助、公助」と似ています。自分たちで決定できることは、自分たちで決定しよう。それができないときはもうちょっと大きな共同体が補完し、その共同体でもダメなときは、より大きな共同体が補完する。でも、中心のいちばん大事なところは、小さな自分が決めるという考え方です。
ところが、それを政策原理として明記するEUでも、個人や地域の力は弱い。結局はいちばん大きいEU事務局が権力を握り、いろいろなことを決めています。でも、この理念と現実の逆転には、やはり「究極の選択」が潜んでいるんです。世論が右往左往する問題を解決するために、EU事務局さえも葛藤しつつ、強権をふるう。
この逆転現象をさらに逆転させて、人々に決定権を戻すべきではないか。政策立案者が抱える葛藤と同じ「究極の選択」を人々に伝え、考えさせ、判断させるべきではないか。そして、一部の意見ではなく、個が葛藤したうえで集合体として意見を表明する。その手段として「究極の選択」という方法は使えると考えました。
ときに全人類が注視しなければならない個人の選択がある
西村勇哉 「スレブレニツァの虐殺」の論文は、この人はこう言ったというような個人の記録が多用されていましたよね。どう決定されたかではなく、個人がどう感じていたかにフォーカスしたのだなと思って読んでいました。
今のお話だと、究極の選択を考えるときには、個人が最後にどう感じるかをちゃんと扱ったほうがいいということなのでしょうか?それとも、個人が感じていたことを記すことで、なんでも決まったとおりにいくわけじゃないということを示したかったのでしょうか。これは、どちらのために個人を取り上げているんですか?
大庭弘継 個人を取り上げた理由は、究極の選択の中には、ときに全人類が注視しなければならない個人の選択があるからです。だから私は、指揮官の選択や葛藤も描き出しておく必要があると思いました。
スレブレニツァの虐殺は、国連PKOオランダ部隊が避難民を守らなかったために、ボスニア・セルビア軍が避難民を虐殺したという事件です。国連の報告書では、ジェノサイドや民族浄化で1990年代に国連は失敗を犯し続けたと書かれています。そこで具体的に名前が出てくるのが、ルワンダ虐殺とスレブレニツァの虐殺のふたつなんです。要は、スレブレニツァの虐殺は、国際政治を大きく動かしたターニングポイントになっているんですね。
隊長の勝手な判断のせいだったのか、それとも、そもそもの指示が悪かったのか。スレブレニツァの虐殺にはいろいろな問題があるとは思うんですけど、間違いないのは、現場のいち個人の判断が虐殺を引き起こし、のちに国際政治にものすごく大きな波となってフィードバックされてしまったことなんです。その転換点を考えるときに、国際政治の使っている言葉や文法だけでは語れないと思いました。それは違う。
僕が、個人の思いや言葉を多用するのは、現場での人間の判断をビビットに描き出したかったからです。上層部の大きな判断に根本的な欠陥があるとき、その問題に対処し動くのが、現場の人間だからです。
「地図で見たらこの町とこの町が近いぞ。走って行ってこい」と司令部が言ったとします。ところが、実際には町と町の間には大きな谷があって渡れないということがある。これを現場の人間が言葉で語っても、その困難さが伝わらない。しかもひどいことに、理解できないものだから、まともな具申(上役に、意見・希望などを詳しく申し出ること)であっても、記録に残らないかもしれない。その事実が記録されなければ、当時の司令部も、のちの歴史家も、そもそも無理という事実を知らないままです。事実を知らずに勝手に物語をつくり、合理的に説明してしまう。結局、無理な命令は自覚もされず、歴史にも残らず、いい加減な教訓が残されてしまう。
ですから、実際に現場に行って突き詰めないと、判断の是非は決められない。僕は、個人にフォーカスを当てることで、実際に現場で何が起こり、何ができたのかを適切に再現したいと考えています。
西村勇哉 それは、現場の判断をもっと大事に扱ってあげるということでしょうか。
大庭弘継 現場の判断を大事にするといっても「ただそのまま現場に任せればいい」は違います。現場の指揮官が勝手に戦争を起こしちゃいました、みたいなことが起こったらまずい。一歩間違うと独断専行を認めることにもなりかねません。
でも、孫子の言葉にも「将は軍に在りて、君命も受けざる所あり(将が軍を率いて戦場にあるときは、たとえ主君の命令であっても受け入れるとは限らないという意味)」という言葉があります。やはり現場が問題に直面する当事者ですので、判断する権限を現場に与えることが肝になると思います。
むろん、司令部からの指示は必須です。でもその指示が、現場に伝わるものになっているか、現場の決断の支えになるかどうか、チェックが絶対に必要です。司令部の指示のせいで現場が右往左往するような状況をつくりだすことはやっちゃいけない。やっぱりバランスが重要なんです。でも、偉そうなことを僕は言いながら、本当に良い組織像というのは、まだ見えていません。
現場の判断が物事を前に進めることもある

西村勇哉 難しい問題ですね。大庭さんは、沖縄の核配備についての論文も書かれていたと思うんですけど。
大庭弘継 あの論文はそもそも「公文書が残されない理由」について書きました。その事例として、沖縄返還に伴う核配備の密約についても取り上げました。
1972年に、佐藤栄作首相とアメリカのニクソン大統領が「こういう条件だったら沖縄を日本に返還してもいい」という交渉をした話です。京都産業大学の先生(若泉敬)が密使となってアメリカに渡り、国務長官だったキッシンジャーとやり取りをするんです。そうしたら、沖縄に核を置いてもいいという密約を結べと言ってきたと。
それに対して佐藤は「そんなのは紙切れにすぎない」「俺が辞めたらそんなものは誰も知らないことになるんだから、欲しいと言うんだったらくれてやる」と言いながら、沖縄への核配備に同意する署名をしたんですね。そして、これは俺の中にしまっておくと言って、文書を机の中にほったらかしにした。正式な外交文書ではないから、記録に残らない。だから、実際にどこまで影響があるのかは、微妙なところがあるわけです。
西村勇哉 密約だから正式ではないかもしれないけれども「こう返答しよう」という判断はしたわけですよね。それってさっきの話でいうと、その瞬間は「現場の独断」だったと思うんです。そして、それによってものすごく前に進んだ。そこでゴネていたら、いつまで経っても沖縄は返還されなかったかもしれないし、無理矢理、核を置かれたかもしれない。正式に置かれてしまったら、のちのちもっと大きな問題になったかもしれません。こういう現場の判断の価値はあると思うんですけど。
大庭弘継 あの密約があったから前に進んだのは、間違いなくあると思います。ただ、それを許せないと思う人たちも数多くいる、なんとも言えないところはありますね。
西村勇哉 究極の選択は、正解がない選択ということですよね。正解がないから、どっちになっても嫌な人はいるし、そもそも何を選ぼうが正解ではない。だけど、選ばないと動かないというのも、確かにそうだなと思って。
大庭弘継 あるいは、選ばないこと自体も選択のひとつで、重要だと思います。たとえば、ルワンダはおそらくほとんどの日本人が一生行くことがない国です。そういう国に対して、無関係な自分たちが何かを選ぶとか何かを議論するというのは大それているんじゃないか。そもそも選択するということ自体がめちゃくちゃ傲慢なんじゃないかという考え方も成り立ちます。
一方で、カンボジアも南スーダンも、日本から自衛隊を派遣したことで、関与を始めた。関与を始めたら、相手に対して責任が生じます。その結果、たとえばカンボジアでは、日本のNGOがたくさん活動していますよね。
あれは、日本が自ら関わったから、そのあとに相手の存在に関心が生まれたということです。今やカンボジアと日本は、簡単には切っても切れない関係にある。あのとき、自衛隊を派遣しなかったら、日本人は、今でもカンボジアへの関心がないかもしれない。だから、関わることによって初めて相手のことをよく知ることもできるし、より大きな何かを生み出すことができるということも、僕はあると思っています。
西村勇哉 わかったような、わからなくなってきたような。わかった気になっているのは、現場の判断は大事だということですね。大きな物事も、結局は小さなところで動いている部分が大きい。だから、もっとちゃんと扱おうということなのかなと思いました。もちろん、正解がないという前提だとは思うんですけど。
大庭弘継 正解はないんですけど、答えの出し方については合意を取っていきたいとは思っています。つまり、実質的正義ではなく手続き的正義をなんとか確立していこうと。
ワクチンの接種問題、人道的介入の是非、小惑星衝突に対して核兵器を使うかどうかなど、究極の選択で扱っているテーマというのは、政治家だけで決めていい問題ではないんです。もちろん専門家だけで決められる話でもありません。やはり関わるすべての人々に、あなた自身の運命の話でもあるとわかってもらい、意志決定に参画してもらいたいと思っています。
その上で「自分はそういう意志決定には関与しません」という人は、そうすればいい。でも同じような問題、生死に関わる問題が生じたとき、「あなたは似た問題に対して他人に自分の生死を委ねたから、今回もいいですね」という選択をした、と自覚もしてほしいんです。
新型コロナウイルスのパンデミックをどう見るか

西村勇哉 そういう意味では、今回の新型コロナウイルスのパンデミックでは、なし崩し的にいろいろなことが決まっているなと感じているんですけど。
大庭弘継 ワクチン接種の優先順位なんかは特にそうですが、誰が決めたんだというところは、僕も不思議です。政府の判断ひとつひとつを、国民が全部追ってチェックするというのは無理な話ですが、言葉にできなくても漠然と抱いている疑問に対して、今の政府はきちんと説明できない人が多く、どうにも信頼できない。そこは本来、政府を信頼しなきゃいけないんですけど。
平川友紀 2014年のシンポジウムで、ワクチン接種の優先順位の話もすでに出ていました。ということは、事前に予見できていた課題だったわけですよね。でも政府の対応にも反映されていないし、私たち自身もそういう問題意識はまったくなく、ここまで来ていた。大庭さんは、2014年の時点でそういうことがないようにとシンポジウムを開催されたと思うんですけど、今のパンデミックの状況を、どう見られているのでしょうか。
大庭弘継 まずオリンピックを1年延期すると言ったときに「えーっ!?」と思いました。だって、スペインインフルエンザのときは、収束するのに2年かかっているんです。収束後から社会の再建をしなければいけないのに、1年延期しただけでできるわけがないと思いました。
あとは、ワクチン接種の優先順位問題と医療資源の配分問題。2020年4月の段階で、スペインやイタリアなどでは医療資源を高齢者には配分しないという意志決定をしました。その是非はともかくとして、日本では「そういうことはやめよう」とか「我が国もそうしよう」といった議論もなく、そもそも明確なトピックとして挙がっていなかったんじゃないかと思います。
ただ、これは今からでも遅くはない。これからも必要になる。そのときのために、きちんと議論しようと思っています。
西村勇哉 シンポジウムの内容を拝見しながら、トピックスはある程度決まっているんだなと思ったんですね。実際にパンデミックが起こっても同じようなトピックスが出てきているということは、予見というよりも、基本的に同じようなことにいつも困っているということですよね。
大庭弘継 そうです、そうです。
西村勇哉 あとは、そこでどんな対応をしたのかがいつも場当たり的だから、毎回「次こそは」って言って終わるみたいな。こんなにトピックスが決まっているなら、絶対に事前に考えられるはずなんだけれども、実際に起きるとこんなにできないものなんだなと思いました。
究極の選択をマイルストーンとして活用する

大庭弘継 僕としては、切迫感や重要性を認識して、究極の選択に参画しようと思ってもらうために、今回のパンデミックに絡めて、SNSを利用した調査をやってみたいなと思っています。
回答数が1,000サンプルだったらまったくインパクトはないけれど、それが1万や10万だったら規模のインパクトで興味をもってもらえるかもしれない。そうすると、究極の選択が単なる有象無象の調査で終わらず、マイルストーンとして活用できる、万人が参加するプラットフォームになるかもしれないなというふうに思っています。
そして「あなたはあのときどういう判断をしました」という記録を残しておくことで……なんて言うのかな。ひとりひとりに責任をもってもらうというか。将来的にはそういう形にしたいですね。
まぁ、究極の選択という仰々しい名前をつけていますが、こうした問題は解決は不可能だけど、なんとなく解消している問題になりそうだとも思います。たとえばワクチン接種の優先順位も、今だから「どうしよう」となっているけれど、将来的にはある程度の共通了解ができあがると思うんですよ。
西村勇哉 確かに。
大庭弘継 だから、問題は解決されるんじゃなくて「当たり前でしょ」っていう形になって消滅していくんじゃないかなというふうには思っています。
平川友紀 常識になるということですね。
大庭弘継 そうです。上宮智之さんの講演を聞いて知りましたが、1860年代に活躍したジェボンズというイギリスの経済学者が『石炭論』という本を書いています。その内容は、イギリスの繁栄の元である石炭は年々枯渇していく、その結果、イギリスは経済破綻して国としてやっていけなくなるから、今から財政支出を減らすために国債の発行を減らすべきだというものでした。これが政府に影響を与えて、ボーア戦争までの数十年間、イギリスは毎年国債を下げていくんですね。ところがご存知のとおり、そのあと石炭は使われなくなって石油に変わっていくわけです。議論の前提そのものが変わってしまった。究極の選択も同じような側面があるんですよ。
私たちは今、未来の子どもたちのために地球温暖化について議論しているけれども、これもまた前提が変わったら、たとえば温暖化ではなく寒冷化の時代を迎えたら「あったの?そんな議論」という話になりかねないわけです。もしこのまま、地球温暖化の議論だけで、逆の議論も考慮していなかったら「うわ、どうしよう。何の判断基準ももってないぞ」ということになるわけですよね。だから、やっぱり議論しなくてはいけないんです。
それに、先ほど西村さんがおっしゃってくださったように、そこで議論される内容やトピックスは、いろいろな問題に共通しているものが多いんです。だから、ある問題を徹底的に議論していたら、ほかの問題にも応用が可能になるということもあるかもしれないなと思います。
西村勇哉 やっぱり記録を残すのは面白いというところに戻ってきたと思いました。たとえば今回の新型コロナウイルスでみんながどんなことをディスカッションして決めたのかということがきちんと記録に残っていれば、次にパンデミックがあったときに「選択肢はこの10個です」という形で考えられるかもしれないということですよね。中身が違う問題でも、同じようなタイプとして扱えるかもしれない。
大庭弘継 そうですね。選択の型は絶対に残ると思います。
西村勇哉 それこそ、ちゃんと記録をとって検証しないといけないところですね。ひとつひとつの個別の話だと、そこに当事者性をもてるかどうかという問題があると思ったんですが、「困りごとはだいたいこういうパターンです」とフレーム化することだったら、すごく現実味があると感じました。そういう意味では、今回のパンデミックでも一定のデータは貯まるような気がします。
一度は現場に関わって、それからものを言う

西村勇哉 しかし大庭さんは、本当に広い視点をもって、いろいろな分野に関わられていますね。
大庭弘継 それでいうとじつは僕、最近は高齢者福祉の研究も考えています。今は、高齢者の孤立が問題化していますよね。それに、コロナでさらに拍車がかかりました。我々の世代はまだいいんです。対面で会うことができなくなっても、こうやってオンラインで会議したり、なんらかの形で補完することができています。でも高齢者はデジタルデバイドの問題があって、切られてしまったまま補完する術をもちません。
だったら我々がZOOMをつないで「もう話しかけられますよ」というところまでもっていって友だちと井戸端会議をやってもらうなど、高齢者のデジタルデバイドの克服を提案してみようかなと考えたりしているんですね。
西村勇哉 ちなみに、なんでそんなことをやっているんですか?
大庭弘継 みんな、少子高齢化が問題だと言いながら、現場に行かない。それはおかしいと思ったので、高齢者福祉の現場にいます。
西村勇哉 確認ですが、これは究極の選択とは全然別の話ですよね?
大庭弘継 いえ。高齢者問題は、もともとやらなきゃいけないと思っていたところがあります。というのは、究極の選択では、残りの時間が短く、また、今を築いた責任者として、必ず高齢者の切り捨てが選択肢になるからです。
僕は、京大では哲学と倫理学の研究員ですが「ケーキの切り分けの倫理(ケーキを切った人間が最後に残ったピースを取ると、公正になる)」というのがあるんですね。高齢者問題に限りませんが、究極の選択を考えるときに、偉そうに現場を含めた未来を語るなら、現場からものを言う(最後にピースを取る)のが筋だろうと思いました。
平川友紀 大庭さんは、とことん現場主義ですね。自分が現場に入って、見て、ちゃんと感じて、そこから研究につなげていくという姿勢が徹底している。
大庭弘継 僕は、高校が福岡のミッションスクールだったんですけど、その高校では週1回チャペルに学年全員が集まって、外から呼んできた先生の話を聞く授業がありました。そこでの話の多くが、厳しい現場での実践報告でした。そして、ある先生が「やっぱり現場に行かないとアカン」とずっと言っていたのが、思春期でしたから、心にこびりついています。
そして今現在、僕が大変尊敬している人で、ルワンダで和解の活動をされている佐々木和之さんがいます。佐々木さんの活動目的は崇高な和解ですが、現地の人たちは日々の生活で大変なので、和解がメインにはなっていかない。そこで佐々木さんは、現場で生活協同組合をつくったり、養豚を教えたりしたんです。佐々木さんの労力は、和解以外の、生活の問題の解決にかなり時間を取られ、はたから見ても困憊していました。
でも、それがいちばん大切なんです。そこに佐々木さんが多くを費したから、加害者と被害者が語らい、ミサに寝坊するぐらい酒を飲みすぎるほど、踏み込んだ和解を目にすることができました。それを見ていて、やっぱり課題を解決するには、現場で有象無象の問題もひっくるめて全部に対処しなければ意味がない、と考えたんです。
哲学的な究極の選択も考える

西村勇哉 大庭さんは、インタビューやフィールドワークをものすごくたくさんやっていますよね。ルワンダに100日行ったとか、今年は40日しか行けなかったからちょっと少なかったとか。だから、大庭さんといえばそのイメージだったんですけど、じつは京大では哲学や倫理学の研究員だと言われて、また印象が変わりました。
大庭弘継 哲学が究極の選択とどう関わってくるかという話を補足させていただくと、最近の哲学トピックに「可能世界論」という議論があります。これは、パラレルワールドみたいな考え方のことです。
僕は、想像の世界の実在性や真実性は認めないといけないと考えています。どういうことかというと、究極の選択にしても、ある選択肢を取ったら、そのルートで次の時間軸が流れていきます。でも、もし別の選択肢を選んだとしたら、当然、別の時間軸が流れていきますよね。
ところが、歴史学者に言わせれば真実はいつもひとつ、歴史はいつもひとつ。まるで、ガッチリ固まったルートがあるかように語る人が結構いるんです。「だったらあのとき、別の選択をして流れるはずだった別のルートに意味はないの?」と。そんなことはない。存在しない世界も実在する世界と同じように、ある一定の点において価値を認めないと議論ができないよねっていうところで、哲学的に、究極の選択の価値を考えています。
西村勇哉 最近勉強する中で知ったんですけど、文化人類学に、未来を扱う文化人類学があるんです。文化人類学で未来を扱うって、何を言っているのかわからないじゃないですか。でも、それがすごくいいなと思ったんですね。
未来は想像の世界だけど、それが今に対してまったく影響を与えないわけではないし、起こったことや起こっていることだけが今を形成しているわけじゃない。その話と可能世界論の話はすごく近いと思いました。可能世界も、その世界があるかというと現実にはないんだけれども、今の自分たちはそこから影響を受けているわけですよね。そこを考えてみることによって選択が変わったり、ある種シミュレーション的に選択することもできるようになる。それはすごく意味があると思っていたので、哲学の世界にもそういう分野があるというのは、ちょっと驚きました。
大庭弘継 ただ、実際に論文や本に書かれている可能世界論を読むと、僕の考えている可能世界論とは問題や関心が被っていないんですよね。だから、それはそれで別にテーマを打ち立てなきゃいけないなと思っています。
僕が現場の事例を引き合いに、「倫理学での徳倫理だ」と言うと「いや、それは徳倫理じゃない」と言われたりしています。不満です(笑)。だから、私の解釈にガガッと引っ張っていきたいなというのは、野心としてはありますね。
いろいろな人の力を引き出したうえでの未来をつくる
平川友紀 取材前のメールのやりとりで、大庭さんはインタビュアーの西村が代表を務めるミラツクに同じベクトルを感じていると書かれていました。今、可能世界論の話を聞いて、ミラツクとはそこで親和性があるのかなと感じました。いったいどこに同じベクトルを感じられたのか、最後にお聞きしてもいいですか?
大庭弘継 ひとつは、タコ壺化した学問の先端ではなく、多岐にわたる現実を取り上げていることですね。現実とがっつり向き合う最先端のテーマを、きっちり取り上げている。それらをグルグルかき混ぜた先に出てくる知見を整理して、みんなで共有できる未来を、形として示そうとしている、と感じました。未来のイメージをつくりだすことが大きなモチベーションになっていると感じたんです。
平川友紀 つまり、大庭さんもそうだということですか?
大庭弘継 そうです、僕もそうです。なるほど、確かに。今気づいた。ミラツクのビジョンに「70億人という数は社会の重荷ではなく、障壁を乗り換えるためのクリエイティブな力へとシフトすることができるはず」と書かれていますよね。僕は、この「70億の力」を形にしたいんです。
たとえば僕の専門は国際政治学です。国際政治では、パワーをもっている国々が集まって、その頂上発信の中で物事が決まっていくんですね。それを誰が動かしているのかというと、そのパワーをもっている国々の政治家たちです。じゃあ政治家たちと国民がどう関わっているのかというと、今は、4年に一度の選挙ぐらいなんですよ。「70億の力」が少数の人間によりデフォルメされた形、それが今の世界。70億が70億である意味がまったくないんです。
僕が自衛隊にいたときに言われた、すごく印象的な言葉があります。
「戦争に勝つための知恵は兵士ひとりひとりの中にある。二等兵から海軍大将に至るまで、ひとりひとりがもっている」
別に階級が下だろうが、若かろうが、誰でもアイデアをもっている。そういうものをちゃんと吸い出して活用する世界。そうじゃないとやっぱりダメだ、と常々思っています。ミラツクも、いろいろな人たちの力を引き出して、引き出したうえでの未来を考えている。
西村勇哉 まさに、はい。
大庭弘継 当然、今だってチッチッチッチッと時間は流れていっています。そして、一歩一歩、未来に進んでいる。つまり、何もしなくても未来には勝手に進んでいくんです。でもきっと、そうじゃない未来を、僕もミラツクも模索しているんですよね。
この記事は、株式会社エッセンスの協力を得て製作しています。
https://esse-sense.com/
何を隠そう、軍事と聞いてしまうとそれだけで目を背けたくなってしまう私がいます。けれども大庭さんのお話を聞いているうちに、少なくとも今、世界を構成する要素として軍事が存在していることは事実であり、何も考えないまま、そこから目を背けていては世界は変わらないのだということに気づかされました。
平川友紀
究極の選択も同様です。難問すぎて、正直目を背けたい。でもそれでは、自分自身で未来をつくることにはならないのですよね。事実を知り、学び、よく考えた先で、私自身がどういう答えを出すのか。そこで出した答えと、その結果もたらされる未来であれば、少なくとも納得して受け止めることができるはずだと思いました。
ひとりひとりの力を信じ、あくまで現場主義を貫いて、必要とあらばその声までも届けようとする大庭さんの姿勢と社会に対する真摯な眼差しに、この世界を変えるのは私たちひとりひとりなのだと、あらためて背筋が伸びた思いです。
今後も産学連携情報プラットフォーム Philo-では、アカデミアの新たな取り組みや、企業活動を捉え直すきっかけを発信していきたいと思っております。今後もご注目ください。
京大オリジナル株式会社
様々な分野の方の声をお届けしていきます。我々と一緒に、遠い未来像を思索し、世界的な諸課題をどう解決していくかについて議論しませんか?
是非、一度お問い合わせ頂き、貴社と一緒にオリジナリティ溢れるプロジェクト企画ができれば幸いです。
〈こちらよりお問い合わせください〉
-1024x460.png)