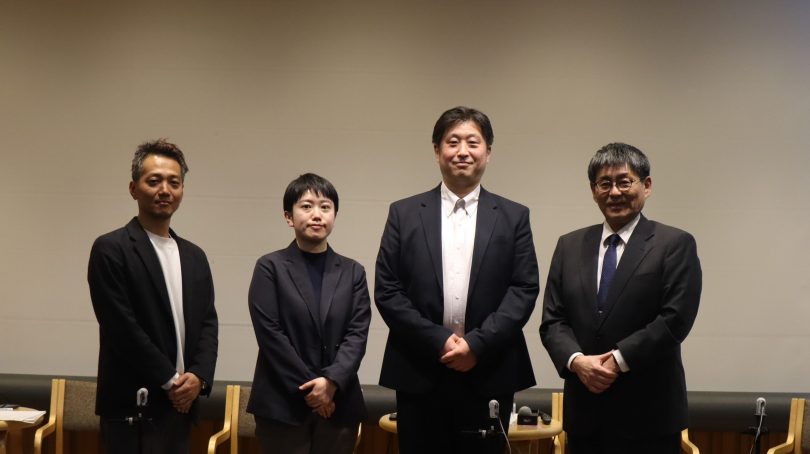topics
アートと研究の境界を超え、最先端技術で「自然の中の美」を発見する。
アーティストであり、研究者でもある土佐尚子さん。芸術とテクノロジーをつなぐ「カルチャラル・コンピューティング」を提唱し、数多くの作品制作や研究を行なってきました。アートと研究の境界を自由に行き来できる土佐さんだからこそ、具現化し、表現できる世界があります。「この先どうなるのか、自分でもまったくわからない」と語る土佐さんに、多くの作品が誕生してきた背景やその根底にある思考の変遷を伺いました。

ライター
平川 友紀

インタビュアー
西村 勇哉

編集者
増村 江利子

土佐尚子
京都大学芸術家/京都大学防災研究所京大災害研究センターアートイノベーション産学共同研究部門特定教授。感情・意識・物語・民族性といった、人間が歴史の中で行為や文法などの形で蓄えてきた文化を、デジタル映像で表現し、心で感じる「カルチュラル・コンピューティング」を提唱し、作品制作・研究を行う。主な作品にニューヨーク近代美術館コレクションの『An Expression』、1993年のArs Electorinicaで招待展示した『ニューロベイビー』、京都五山建仁寺に奉納した『静寂』『雲の上の山水』、MIT Center for Visual StudiesのFellow時代に制作した『ZEN Computer』、ハイスピードカメラを使った『Space Flower』『Genesis』などがある。2016年度文化庁文化交流使の拝命を受け8カ国10都市を表敬訪問し、NY Times Squareのビルボードで毎夜『Sound of Ikebana』を1ヵ月間上映するなど国際的に活躍している。平成30年〜31年、内閣府総合科学技術・イノベーション会議専門委員。
シュルレアリスムへの関心からアートの道へ

西村勇哉 土佐先生に最初に伺いたいのが、中高生時代の話です。いつ頃からアートに興味をもたれたのでしょうか。
土佐 尚子 中高生の頃は何の苦労も知らなかったし、妄想だけしていればよかったから、いちばん自由で幸せでしたね。私は、ものすごく妄想するタイプの子どもだったんです。本が好きで、そこからイメージを膨らませていました。おもちゃはすぐに飽きるけど、本は一冊一冊書いてあることが違うから、いつまでも飽きずに読むことができたんです。それと、母親がアートが好きだったので、クラシックの演奏会や美術館には、早くから一緒に行っていました。演奏会は、眠るために行っていたようなものでしたけどね。
中学に入った頃に、私自身がアートに興味を抱き、絵を描くようになりました。アートが好きになるか嫌いになるかは、ひとえに小中高の美術の先生と合うか合わないかだと思います。それは人間的相性という意味ではなく、その先生がつくっている作品との相性という意味です。私は、中高の美術の先生とすごく相性がよかったんですね。その先生は、シュルレアリスム(超現実主義。戦間期にフランスで起こった、作家のアンドレ・ブルトンを中心とする文学・芸術運動)の画家でした。美術室の裏に行くと、人間のシルエットの中に、ガバッと開いた口だけが描かれているような絵が置いてあったんです。「この先生は、いったいなんでこんなものを描いているんだろう?」と思ったところから、シュルレアリスムに興味をもちました。ダリやエルンストの作品を見て衝撃を受けましたね。
西村勇哉 小中高はみんな違う美術の先生だったのですか?
土佐尚子 小学校は違う先生で、中高は一緒ですね。中高の先生は、今も福岡の土着の画家です。そういう良い出会いがあったのと、やはり、アートを大事にする家庭環境であったことは、大きかった気がします。
誰もが認めてくれる仕事を隠れ蓑にしてアーティストになる

西村勇哉 その後、大学に入られますよね。アーティストの道に進もうと思われたきっかけはあったんでしょうか?それともやりたいことをやっていったら、自然とそうなっていったんでしょうか。
土佐尚子 自然と、ですかね。中学生の時に、シュルレアリスムの世界に衝撃を受けて、こんなことをやって生きていけたらすごく面白いなぁと思った。でも、アーティストのなり方って、誰も教えてくれないんです。
今は違うのかもしれないですけど、その時代はアーティストなんて目指していると、それだけで周りから怒られるんです。「アートみたいに食べていけない世界はダメ」と言われることは本当に多かった。特に、女性アーティストで成功している人はほとんどいませんでしたからね。しいていえば、オノヨーコさんとか草間彌生さんとか、そういうすごい人たち。「これは尋常じゃない世界だな」と思いますよね(笑)。ただ、成功した有名な人たちは、ちゃんと作品が売れて仕事になっているわけです。すごく面白いし、自分もそうなりたい。でもなり方が全然わからない。どうすればいいんだろうと悩みましたね。
西村勇哉 そこで、実際にどうされたんですか?
土佐尚子 とにかくまず、作品をつくりました。私は新しいもの好きだったので、何をやろうかと考えたときに興味をもったのが、テクノロジーやコンピューター、ビデオアートでした。アート&テクノロジーの世界を知ったのは、かなり早いほうだったと思います。
最初にビデオアートに触れた場所はなんと図書館です。ビデオアートが図書館の本と同じような扱いだったんですね。そこで、ナム・ジュン・パイクの作品などを観て「こんなアートがあるんだ!」と知り、ビデオアートに目覚めて、同じ作品を何度も観ながら研究していました。
一方で職業的には、中学か高校の美術の先生になるのがいいのかなと考えました。先ほども言ったように、アーティストになることを周囲が簡単には許してくれなかった時代です。教師のように、誰もが認めてくれるような仕事を隠れ蓑にしながら二足の草鞋(わらじ)でやっていくことが、アーティストになる唯一の方法だったわけです。私はそんなに反抗的な性格ではなく、9割の人を敵に回してもアーティストになってやるというタイプではなかったので、堅実な道を選びましたね。
ただ、実際に中学校に教育実習に行ったら、美術の授業は週に1回しかないので、生徒からすると私は給食の時に来るだけの先生に見えたみたいなんです。そう言われて、かなり自尊心が傷つきました。それに、非行が社会問題になっていた時期だったこともあって、美術の授業は遊びみたいに思っている生徒がほとんどでした。勉強する気が全然ないので「こんな状態でどうやって教えたらいいんだろう」という感じです。そのうえ、今も問題になっているとおり、教師はすごく仕事が多いんです。実際の現場を見たら「これじゃ忙しすぎて、自分の作品をつくる暇なんてないな」と。
じゃあどうしようかと考えて、大学の先生ならもう少し自由があるんじゃないかと気がつきました。調べると、大学教授になるにはドクターをもっていなきゃいけないということだったので大学院に行くことにして、そのまま研究者の道に進んだんです。
アーティストも研究者もプロセスは同じ

西村勇哉 今日聞こうと思っていたことのひとつが、まさにそこでした。20代の頃から大学で講師をされていたので、ずいぶん早い段階から教育分野にいたんだなと気になっていたんです。今の話でその謎が解けました。
でもそうなると、教えることと研究することと作品をつくることがうまい具合に仲良くなってくれないと、全部を同時にはできないんじゃないかなと思いました。振り返ってみて、研究者であったことがアーティストとしていい方向に作用したことはありましたか?
土佐尚子 めちゃくちゃあります。というか、一緒だと思いますよ。アーティストも研究者も、最終的にインテグレーション(統合、統一)しますよね。研究者は「これはなぜなんだろう」という疑問から始まって、調査し、分析をします。新しい説やモデルを組み立てて何かをつくりあげ、最後に論文を書いて出す。アーティストが作品をつくるときも、だいたい同じような工程を辿っています。
アーティストが研究者と唯一違うところは、ダメだと思ったら全部を崩して、また最初からやり直すところです。だから工学系の研究者からすると、アーティストはとんでもないやり方をしているように見えるみたいですね。彼らは「この方法はおかしい」と思ったら、1歩か2歩戻るんだそうです。そこは違いますね。
西村勇哉 途中で崩しちゃうんですか?それとも、一旦は作品としてつくるんですか?
土佐尚子 最初の頃は、もったいないと思ってつくっていたこともありました。インタラクティブ系の作品であれば、途中までのシステム設計が使えるので、戻ってやり直すこともできるかもしれません。でも、中途半端に中途半端を乗せても、ろくなものはできあがらないということがわかったのでやめました。特に今、私がやっている「Sound of Ikebana」は、素材が命のところがあります。一発勝負なのに、出来の悪い素材に一生懸命何かやろうとしても、やっぱり一緒なんです。だからダメだと思ったら、結構すぐ崩していますね。
渡米したことで、日本文化に興味をもつ
西村勇哉 順調に活動されていたと思いますが、2002年には、マサチューセッツ工科大学(以下、MIT)に招聘されてアメリカに行かれましたよね。
土佐尚子 朝日新聞の記者だった坂根厳夫さんの『遊びの博物誌』や『科学と芸術の間』といった本が好きでよく読んでいたこともあり、アート&テクノロジーの本場がアメリカだということは、20代前半にはすでに知っていました。MITの「Center for Advanced Visual Studies(先端視覚技術研究所、以下CAVS))」では、私が衝撃を受けたナム・ジュン・パイクをはじめ、たくさんのアート&テクノロジーのアーティストが研究したり、作品を発表したりしています。だからMITはずっと「どうやったらここに行けるんだろう」と思っていた場所でした。
「日本でやっていてもダメだな」と思い始めたのが30代後半ぐらいです。なぜかというと、同じようなことをやっていても、注目度が全然違うんですね。「やっぱりMITみたいなところに行かないと注目されないんじゃないか」「アメリカに行かないと一人前になれないんじゃないか」と考えるようになっていました。ハッキリ言ってしまうと、日本がダサいと思っていたんです。だからその頃は、日本を脱出することばかり考えていました。そして無事にMITに招聘され、アメリカに行くことができたんです。
西村勇哉 そういう意味では、昔からの夢が叶ったということなんですね。ちなみにMITでは、日本文化を研究領域の真ん中に設定されました。なぜこのタイミングで、日本文化を真ん中に置いてみようと思われたのでしょうか。
土佐尚子 MITからは、年間研究費を400万円渡すから、日本のアート&テクノロジーを見せる作品をつくってMITの博物館で展示してくださいと言われていました。MITに行く前は京都に住んでいたのですが、そう言われて何をやろうかなと考えているときに、たまたま国立博物館で雪舟の大回顧展をやっていたんです。それでふと「山水画の世界って、まだ誰もVRでやってないよなぁ」という、文化の“ぶ”の字もないようなことを思って、極めて打算的な視点で観に行ったんです。でも実際に観たら「これこそVRでやるべきだ!」と思って。
そのあとすぐ渡米したんですが、アメリカに行ったからって、服を着たり脱いだりするように「今日からアメリカ人になるんだ」というふうにはできないわけです。日本の当たり前とアメリカの当たり前はもちろん違うし、思考や味覚はそう簡単には変わりません。すると今度は、アメリカから見た日本が見えてくるんです。それは、今までの私からは見えていなかった日本の姿でした。“わびさび”のなんたるかや和食の繊細さなど、日本独自の良さがわかってきたんです。
ボストン美術館に行ったときに、岡倉天心がつくった日本庭園がすごく荒れていたというできごともありました。ガードナー美術館の日本庭園もやはり荒れていて、同じ日本人として「これはまずいだろう」と思いました。そうなってくると「もうちょっとちゃんとしなきゃいけないだろ」という憤りと「日本も意外といいところがあるよな」という懐かしさとが合体してくるんです。
私はそれまで、日本文化に親しみをもったことなんてありませんでした。山水画をなぜ描くのかということさえも知らなかった。でも、興味をもっていろいろと本を読んでみたら、山水画は禅の心得を学ぶための入門としてやるものだということがわかりました。つまりあれは修行なんです。そこからどんどん面白くなってきて、知識をアップデートしていく中で禅に惹かれていき「ZENetic Computer」という作品ができました。
アートとテクノロジーの間には文化がある
平川 友紀 客観的な視点が生まれたことで、日本文化の良さに気づいていったわけですね。
土佐尚子 もっと言うと、アートとテクノロジーの間に「文化」があると気づいたのは、その前にやった「インタラクティブ漫才」という作品でした。その元となったのが、私が博士号を取ったときに制作した「ニューロベイビー」という作品になります。「ニューロベイビー」は、声の抑揚による感情認識のAIです。それ自体は、極めて工学系の研究でした。その技術をそっくりそのまま使い、吉本興業とコラボして、漫才のツッコミコンピューターをインタラクティブにつくったんです。それを手土産にMITに行きました。
そうしたら、当時のボストン領事館の方から「春フェスタというイベントがあるからこの作品を出してほしい」と頼まれたんですね。ところが、日本人だとあれだけ笑っていたものが、アメリカ人にやってもらうと誰ひとりとして笑わないんです。これは大変だということで、あれこれ原因を考えた結果、英訳を日本人がつくったからじゃないかと思い至りました。そこで、ボストンの人気コメディアンに、これと同じような意味でもう少しボストンコメディふうの言い回しに変えてほしいとお願いしました。するとすぐに、みんなが笑ってくれるようになったんです。
土佐尚子 コメディは特に顕著なんですけれども、文化が理解できないと笑えないんだということに、そのとき気がつきました。そこで文化の重要性に少しは気がついていて、もっと深いものだということがわかったのは、ボストンに行って、日本文化に興味をもってからだったと思います。
文化というのは、遥か昔から遺伝子レベルで続いていて、だからこそ、これを無視することはできない。一方で文化は、テクノロジーによって扱えるということも感じましたね。
西村勇哉 以前、漢字の脳内イメージの研究をされていましたよね。報告書を読んでいて面白いなと思ったのが、土佐先生はアーティストだから、理論だけではなく、実際にイメージをつくれてしまうという点でした。僕は社会科学系の人間で、ものをつくることができません。だから一生懸命、言語の世界で頑張ろうとします。でも何かをつくることができて、それをベースにさらに研究を進めることができるというのはすごくいいものだろうなと思いました。アーティストとして研究者の側面が活きてくるだけでなく、研究者としてアーティストであるという逆の側面が活きてくることもあるんじゃないのかなと。
土佐尚子 そうですね。研究へのフィードバックは考えやすいんじゃないかなと思います。ここの詰めが甘いからこれを直そうとか、あの分析はこういうふうに変えられるんじゃないだろうかというふうに、新しい発想につなげやすいところがある。でも、思いついたことをすぐにやっちゃうようなアーティストと比べると、私はやっぱり、論理的なほうなんじゃないかなとは思いますね。
アートは先が見たいという欲求があってやるもの
西村勇哉 作品を順番に見ていったんですが、人の無意識を可視化した「アンコンシャスフロー」という作品がすごく好きでした。
土佐尚子 なんであれをつくったかというと、初期の「ニューロベイビー」や「インタラクティブポエム」といった作品は、インタラクティブアート(双方向芸術。観客を巻き込むことで表現を成立させるアートのこと)なので、いろいろな人に実際にやってもらうことになるんですね。でも人間って、ああいうものより上位に立ちたいと思うんです。子どもでさえそうなんですよ。
あるときNHKの番組で、反応が10パターンぐらいしかない「ニューロベイビー」と、人間が声優として饒舌に話しかけるモーションキャプチャーの女性キャラクターのCGを並べてみました。最初、子どもたちは両方に話しかけに行くんです。ところがCGのほうは「君たち宿題はやったの?」とか、なんとも流暢に話しかけるわけですよね。そうするとだんだん離れていって、今度は反応が限られるニューロベイビーに向かって「バーカ」とか言い始めるんです。
大人は大人で、ウソをついたり、試そうとしたりします。悩みを話し出す人たちもいましたね。「人間ってそういうもんなんだなぁ」と思ったときに、「これで大丈夫なんだろうか」と思ったんです。そうじゃなくて、その人の本当の姿をセンシングしたかった。そのためには、生理情報と心理情報の両方が大切だと思い、生理心理学者と一緒につくったモデルが「アンコンシャスフロー」なんです。
西村勇哉 今でこそ近いことをやったり、やろうとする人はいっぱいいると思います。でも20年前にすでにやっている人がいたということに驚いたんですね。さきほど、早くから禅に興味をもたれていたと伺って、なぜそんなに先に行けたのかは垣間見えました。でもやっぱり、それ以上にアーティストであることは大きかったんじゃないのかなと。作品をつくって世の中に出すからきちんとフィードバックがある。実際の反応が見えるから「じゃあこういうことができるんじゃないか」と考えてすぐ次に進める。そのスピードが、研究者とアーティストの両方があるとすごく早いのかなと思いました。
土佐尚子 それはあるかもしれませんね。アートは、先が見たいという欲求があってやるものなので。直感的に「こうなんじゃないか」と仮に定めて、帰納的に戻ってくるような感じのところはあるかもしれないですね。
インタラクティブアートはシミュレーションにしかならない
平川友紀 長年、インタラクティブアートを研究されていたと思いますが、10年ほど前からガラリと作品の方向性を変えましたよね。現在も取り組んでいる「Sound of Ikebana」は、最新のテクノロジーを活用しながらも、よりアートの要素が強くなっていると思います。作品集『TOSA RIMPA』の中で、インタラクティブアートをずっとやってきたけれどもパッタリやらなくなって、そこからアートに回帰していったと書かれていました。この大きな方向転換には、何か理由があったのでしょうか。
土佐尚子 「ニューロベイビー」は、幸か不幸かいろいろなメディアで取り上げられ、社会的にすごく注目されました。そのために、やめるにやめられなくなってしまい、10年近く続けなきゃいけなくなったんですね。結局、1993年から2002年ぐらいまでやっていました。
2001年には、「ニューロベイビー」の感情認識をドラえもんに応用し、2001年に藤子不二雄とコラボレーションをする「ドラえもん」の展覧会で、「助けてドラえもん」という作品を作り、1時間待ちのインタラクティブな対話体験型作品にもなりました。

土佐尚子 当時よく(ニューロベイビーは)「成長してますか?」って聞かれたんです。成長って、何をもって成長っていうんだろうと思いましたね。私もハマるタイプなので、成長とは何かを調べ出したらよくわからなくなって、ぐるぐる回って、いつまで経っても開発まで辿りつかない。さらに「感情とは何か」までいってしまったんですけど、これも何重にもあったんです。そういうことを考えれば考えるほどニューロの計算は遅くなって、何をやっているのかわけがわからなくなり、あっという間に10年が過ぎていました。
そうすると人間だったら、10年前に産まれた赤ん坊が10歳になっているわけです。かたや、自分が生み出した「ニューロベイビー」の育ちの遅いこと。生身の人間のほうが成長が早いというのは「研究者としてダメだな」と思いました。
その後、MITでやった「ZENetic Computer」がアプリになった姿を見て「私がやりたいことってアプリだったっけ」ということも考えました。だって、アプリってサービスですよね。「それは違うはずだよな」と。
この手の研究は落とし穴がいっぱいあって、ちょっと間違えるとすぐエンジニアリングのほうにいって、ロボットやAIの研究者になっちゃうんです。私はそれだけは、一生懸命避けてきたんですね。
平川友紀 アーティストであり研究者でもある土佐先生ができることを考えた時に、アートに戻っていこうと思われたということでしょうか?
土佐尚子 そうですね。ビデオアートをやっていた時に「なんでインタラクティブでやるんだ」とよく聞かれました。「ニューロベイビー」を出した時は「こんなのアートじゃない」とも言われました。それでもいったんはそっちの方向に行ったんだけれども、結局インタラクティブアートっていうのは、コンピューターのブラックボックスでやっている以上、シミュレーションにしかならないんです。現代美術家や美術評論家とそういう議論をしたこともあって「確かに自分のやっていることはシュミュレーションにしかならないのかもしれない」と思うようになっていました。そして、インタラクティブアートが、技術の整備によってアプリでもできるようになった瞬間に、はっきりと「これは自分のやることではない」と感じたんです。それで、取り組んでいた研究からスルスル抜けていったところがありますね。その後、物理的な自然界に目を向けるようになって、「インビジブルビューティ」という新たなテーマが出てきました。
最先端技術を使って自然の中の美を発見する
平川友紀 なぜ物理的な自然界に目を向けるようになったんですか?
土佐尚子 これは私の個人的な見解なんですが、「美」には3パターンほど発見の仕方があると思っています。
ひとつめは昔、レオナルド・ダ・ヴィンチがいたような時代から、アーティストが発見して描いてきた自然の中の美。
ふたつめは、いろいろな人がつくったアートに対して、科学者や数学者が発見する、原理や法則の美。
3つめは、その美の法則や原理といったものを、コンピューターサイエンティストがコンピューターに乗せて可視化し、新たにつくる(発見する)美。
今は、この3番目の時代まできています。そして私は、20代の頃からそれをやってきたと思っています。でもそっちはもう、私がやるよりもずっと早く、若い人がいろいろなことをやっていくはずですよね。じゃあここにきて、私はひとつめの「自然の中の美」を発見しようと思いました。しかも、最先端技術でもってしか見ることのできない美を自然の中から発見する。そっちのほうが面白いんじゃないかと思ったんです。

土佐尚子 最初の頃は模索しながらいろいろなことをやりました。彫刻をつくったこともあるし、写真を撮っていた時期もあります。そしてあるとき、ハイスピードカメラに出会うんです。よくよく考えると、MIT博物館にストロボを発明したハロルドエジャートンの有名なミルククラウンの作品やハイスピードカメラ関係の作品が常設展示されていたので、無意識に感化されていたのかなと思います。その出会いから生まれたのが「Sound of Ikebana」です。
西村勇哉 なるほど。じつは以前、京大のラボに伺ったことがあるんです。そこで「Sound of Ikebana」を拝見した時に、ペンキが飛び散っていたり、車のフロントガラスが割れていたり、これはいったい何を研究しているんだろうって、あんまりよくわからなかったんですね。でも土佐先生がやられてきたことを最初から全部辿っていくと、ちゃんと流れがあって「Sound of Ikebana」になったんだということが、よくわかります。
土佐尚子「Sound of Ikebana」もすぐに成功したわけじゃなくて、失敗の連続だったんです。1年近くやってもうまくいかなくて、自分は片付けをしているだけなんじゃないかと思い始めていました。最初は学生も手伝ってくれていたんですけど、いい形が出てこないと萎えますよね。最後は私ひとりでやっていて、これはダメかなと思った時に、液体の量を増やして以前のやり方とは変えてみたら、すごい形が生まれてきたんです。
その時に「この作品のタイトルは『Sound of Ikebana(音から生まれた花)』にしよう」と決めました。サイモン&ガーファンクルに「サウンド・オブ・サイレンス」という曲があります。音なんだけど聞こえない、というふうに、違うものを組み合わせている感じがいいなと思いました。






Sound of Ikebana、洋服になる

土佐尚子 「Sound of Ikebana」は動画をつくることから始まり、それをプロジェクションマッピングにしていったんですが、現在はさらに進化しています。じつは今、洋服をつくっているんですよ。
西村勇哉 洋服ですか!
土佐尚子 そうなんです。だから私は今、夜な夜な、パタンナーの仕事をやっています。ファッションの聖地、東京・原宿の東急プラザ表参道原宿で、ファッションショーもやりました。
なんと、表千家の次期家元、池坊専好さんが、この「Sound of Ikebana Fashion」を気に入ってくれて、パフォーマンスのときに着たいって注文してくださったんですよ。すごいですよね。サウンドオブ生け花、本家本元とつながる(笑)。本当に面白くて、最近はこればっかりやっていますね。ちょっとしたアートイノベーションだなぁと思っています。

西村勇哉 ファッションショーの映像を拝見していたら、「Sound of Ikebana」って炎とか木陰の揺らぎとか、自然物の美しさに似ているんだなと気づきました。
土佐尚子 それは嬉しいお言葉。「Sound of Ikebana」は、一種のカオス現象ですからね。服にすると、人って動くので、それがまた面白いんですよね。前身頃と後ろ身頃があって、パターンの中に絵をはめていくんですけど、つくっているときは良さそうに見えるものが、実際に服になって人が着ると見え方がまったく変わるんです。立体的になったときに美しいかどうかはまったく別で、そこを予測してつくらないといけないのがすごく難しかったですね。
西村勇哉 国立博物館の壁に映したプロジェクトマッピングがすごくカッコいいと思っていたんですけど、洋服という物質として出てくるとまたすごいですね。目では見えない音を、まず動画として見える化したわけですよね。それを止めて画像にして、さらに服にプリントして物質化する。すごく不思議な工程です。これはつまり、音を着るということですよね。
土佐尚子 そうですね。音を着ます。


西村勇哉 理化学研究所でも働いていて、先の未来についてのシナリオをつくるという仕事をしているんです。その中のひとつで「音をまとう」というシナリオをつくりました。音は絶対に着れるというか、まとえるはずだと思ったんですけど、これが誰にも理解されなかったんです。だから今のお話は感動ものですね。「Sound of Ikebana」の服なら音をまとえる。良かった、書いておいてと思いました。
アート&テクノロジーなら、事業化も違和感がない

西村勇哉 でもなぜ突然、洋服をつくることにしたんですか。
土佐尚子 これは、セイコーエプソンとの共同研究ですね。「Sound of Ikebana」は、もともと京大オリジナルと一緒に事業化を試みています。産声でつくる「Sound of Ikebana」の販売などもやっているんですが、ご存知ですか。
西村勇哉 もちろん知っています。

土佐尚子 普通なら、アートは事業化の手前までだと思うんですが、アート&テクノロジーの世界に入るとちょっと違うんですね。話が戻ってしまいますけど、MITのCAVSは、戦争でアメリカに亡命してきたバウハウスのジョージ・ケペッシュがつくったんです。産業復興とアートの両方をやろうとしたのがバウハウスで、私もその末裔にいるわけです。だからアート&テクノロジーだと、事業化の流れが違和感なくすんなりいくんですよね。ここら辺の感覚が、アートや工学だけの人とはちょっと違って、私がいろいろなものにつながっていけるところかなと思いますね。
たとえば、これも最近の話なんですが「DUREN」という会社が「Sound of Ikebana」をバッグにして販売することになりました。この会社のオーナーは、「UBUGOE by Sound of Ikebana」をテレビで観たときに「生命力を感じた」って言うんです。コロナ禍で、人と人があまり触れ合えない時代に「こういう生命力を感じるバッグをつくりたいんだ」と。いいこと言うなと思ってコラボに合意したんですけどね。つまり「Sound of Ikebana」は、非常に広がりが出てきていて、事業化といっても、作品をギャラリーで売るような昔のビジネスからはどんどん離れていっていますね。

説明しなくてもわかるものをつくりたかった
土佐尚子 でも、私が今回いちばん驚いているのは、こんな洋服は、変わった人や特別な人しか好きにならないだろうと思っていたのに、意外と一般の人が欲しいって言ってくれることなんです。
西村勇哉 普通にカッコいいですからね。
土佐尚子 今まで「Sound of Ikebana、気持ち悪い」と言っていた人が、洋服には関心をもってくれます。「気持ち悪い」から、いきなり「カッコいい」になるんですよ。私はそれがいちばん嬉しかったですね。
だからみなさんから「これはビジネスになるよ」と言われるんですけど、私としては純粋に、こんなことができて非常に面白いなという気持ちが大きいです。あとは、ファッション業界はまだアナログな部分が多いんですけど、私みたいなデジタル寄りの人間が入ることによって、デジタル化が進むことにつなげられるんじゃないかと思っています。
平川友紀 アート&テクノロジーの領域でいろいろやってきた中に、産声だったり洋服だったり、リアルなものが介在してきて難解じゃなくなった感じがありますね。
土佐尚子 そうです!まさにそれを求めていったんです。説明しなくてもわかるもの。本当に今回いちばん嬉しいのは、一般の人に関心をもってもらえていることですね。
今までの作品は知る人ぞ知るっていう感じのものばかりでした。インタラクティブアートをやっていたときも、お客さんって、説明だけ聞いて「ふーん」って言って、インタラクションしないで帰っちゃうんです。それがすごく嫌でした。だから「Sound of Ikebana」を始めるときには、まず、驚きを前面に出そうと思っていました。そのあとに「えっ、これはなんなの?」と聞かれたら、そのときに説明すればいいと思ったんです。
平川友紀 もともと、そういうことを意図してファッションに取り組まれたんですか。
土佐尚子 いや、最初にエプソンとやろうとした目的は、じつはプロジェクターです。私はプロジェクターをよく使うので、手元にあったらいいなと思うじゃないですか。それには共同研究だ!と思い、声をかけました。つまり、本当はプロジェクターの担当者とつながりたかったんです。そうしたら、なぜかデジタル捺染(なっせん)の担当者とつながったんですよ。
平川友紀 うまくいかないものですね(笑)。
土佐尚子 でも、その担当の方たちがすごくサポートしてくれたんです。研究室にも機械を入れてくれましたし「こんなことができますよ」「あんなことができますよ」って私の作品をプリントしたサンプルをたくさん持ってきてくれました。「そんなに熱心にやってくれるなら、ちょっとやってみようかな」という気持ちになったというのが正直なところです。だけど実際にやってみたらすごく面白くて、学生もみんなノッてきて、今があります。もしあの方たちがいなかったら、私はこんなことやっていなかったと思うな。
「一体何になるんだろう」と思うことほど大きな見返りが来る

平川友紀 何かのインタビューで「結果はあとからわかる」とおっしゃっていましたが、まさにそれですね。
土佐尚子 そうです、そうです。あのね「これをやって一体何になるんだろう」というようなことほど大きな見返りが来ますよね。
今回のはまだわかるほうですよ。いちばんわけがわからなかったのは「ZENetic Computer」です。あの時はもう、自分で自分が何をしているのかがわからなかったですからね。今も結構、それに近いところまではきているので、我ながらこの先どうしていくのかなぁという感じがしています。だって最近ずっと調べているのは、川久保玲さんのことですからね。
本当に今は、望んでやってきたことと望んでいないけどきちゃったことが合体して進んでいます。こんな展開は、一年前にはまったく考えていませんでした。なるようになってここまできたので、この先のことはまったく想像できないし、自分が何者なのかが、もはやわからなくなりつつあります。

土佐尚子 ただ、個人的には、前代未聞のファッションショーを世界中でガンガンやりたいなと思っています。その第一歩がニューヨークですね。2022年のファッションウィークに、「Sound of Ikebana Fashion」のファッションショーをやる予定です。それが、この先にある第一目標ですね。
この記事は、株式会社エッセンスの協力を得て製作しています。
https://esse-sense.com/
インタビュー後、「ぜひきてください」とお誘いいただき、まだ開催中だった東急プラザ表参道原宿のファッションショーを観に行かせていただきました。ふたつの壁一面に「Sound of Ikebana」の映像が映し出され、映し出された映像を素材にした「Sound of Ikebana Fashion」を身に纏ったモデルさんが歩いていきます。「Sound of Ikebana」の一瞬の美しさが映像とリンクし、さらにモデルさんが動くたびに見え方が変わっていく。それはまるで、映像や洋服という別の手法によって、瞬間の美に再び生命が与えられ、うごめき出したかのようでした。最新のテクノロジーを駆使したアートであるはずなのに、どこか生々しくリアルな美しさを感じたのは、おそらく「見えないけれどもある」ということを確かに示してくれたからではないでしょうか。「Sound of Ikebana」という作品は、さまざまなつながりや出来事から事業化され、ファッションという新たな表現にも結びついていきました。縦にも横にも、境界を超えていく。その力強さと軽やかさが土佐さんの魅力であり、アート&テクノロジーの面白さなのだと思いました。この先にいったい何が起こるのか、今から楽しみでなりません。
平川 友紀
今後も産学連携情報プラットフォーム Philo-では、アカデミアの新たな取り組みや、企業活動を捉え直すきっかけを発信していきたいと思っております。今後もご注目ください。
京大オリジナル株式会社
様々な分野の方の声をお届けしていきます。我々と一緒に、遠い未来像を思索し、世界的な諸課題をどう解決していくかについて議論しませんか?
是非、一度お問い合わせ頂き、貴社と一緒にオリジナリティ溢れるプロジェクト企画ができれば幸いです。
〈こちらよりお問い合わせください〉
-1024x460.png)